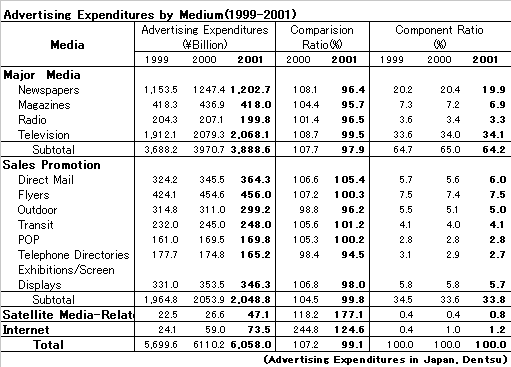|
NSK ニュースブレチン オンライン ------------------------------------------------------------------- 46万人が日本の新聞配達を担う
その新聞配達を担っている新聞販売店従業員の数は46万4827人。新聞協会が2001年10月に実施した調査の結果明らかになった。 新聞は、新聞発行本社から新聞販売店に直接届けられ、販売店従業員の手で配られる。朝刊は朝6時ないし7時ころまでに読者の家の新聞受けに入れられる。勤めに出る人も、家を出るまでに新聞に目を通せるよう、配達時間は厳しく管理される。 その配達業務を中心となって担っているのは、パートの女性で42%。ついでパート男性が29%である。本調査の第1回が行われた1963年は、新聞少年(18歳未満の中学・高校生)が73%を占めていた。新聞少年は年々、その数もウエートも下げて来て、今回調査では8%にまで減少した(図参照)。それに代わり中心になったのがパートの女性だ。比較的短時間で収入が得られるため、家庭の主婦にも格好の仕事になっている。 ここ数年、従業員の数は若干減少気味にあるが、新聞少年に代わっておとなの従業員を増やし、新聞用紙の軽量化を進めて配達労務の軽減を図るなど、配達システムを守る努力が続けられている。 ボーン・上田賞を2氏に授賞 「ボーン・上田記念国際記者賞」選考委員会は2月14日、2001年度の同賞を、朝日新聞アジア総局長の宇佐波雄策(うさなみ・ゆうさく)氏と、共同通信モスクワ支局の及川仁(おいかわ・ひとし)氏に授与することを決めた。 同賞は、優れた報道活動で国際理解に貢献したジャーナリスト個人に贈られる。 宇佐波氏は、20以上一貫してアジア報道にかかわり、各地域の政治、経済、社会問題の報道にとどまらず民族、宗教、歴史に深い関心を寄せ、住民の息づかいや社会のにおいが感じられる文化的な記事を数多く執筆。またアフガン危機が始まるとイスラマバード、次いでカブールから、多民族社会の底流を踏まえた深みのある報道と論評を続けたと評価された。 及川氏は、米同時テロ後の9月22日、アフガニスタン北部に入り、日本の他社が現地入りするまでの約2週間、日本人の目でアフガン情勢を日本に伝える貴重な存在となった。また、10月7日夜、米軍によるカブール空爆が同日深夜にも開始される可能性があると速報。空爆は間もなく開始され、他国の報道界からも高い評価を受けたことなどが授賞理由。 この賞は日米協力による自主的な世界ニュース通信網の確立に献身したマイルズ・W・ボーンUPI通信社副社長と上田碩三元電通社長が1949年1月、東京湾の浦安沖で突風により遭難されたのを惜しみ、両氏の業績を顕彰するため、日本の報道界およびボーン未亡人の拠金により、アメリカのピュリツァー賞にならって、1950年に設立された。毎年度、優れた報道活動で国際理解に貢献したジャーナリスト個人に贈られている。電通は、共同通信、時事通信とともに戦前の同盟通信社を前身とする。
「日本はアジアとヨーロッパがミックスされている」(クリスチャン・サイエンス・モニター紙のリンダ・フェルドマン論説面編集長)、「日本の政治・経済状況や日米関係に関する取材をした。日光東照宮の三猿に興味があったので、民俗学の専門家から話を聞いた」(シカゴ・トリビューン紙のマイケル・マクガイア編集局次長代理)などと語った 一行は、東京で、中山太郎衆議院議員(日米議員連盟会長、憲法調査会会長)産経新聞東京本社、NTTドコモなどを訪問した後、2月19日から3日間沖縄を訪れ、地元紙の琉球新報社や沖縄タイムス社の記者との懇親会に参加、普天間基地、首里城、平和記念公園などを訪れた。その後、4日間京都に滞在し、帰京して明石康・元国連事務次長と懇談した。 日本側記者団6人は2月13日から米国を訪問、国防総省、ニューヨーク・タイムズ、CNN、シアトルタイムズなどを訪れ、テロ後のアメリカを視察した。日米両国の記者団は2月28日から2日間、ハワイの東西センターで総括討議を行った。 本交換計画は、新聞協会と米国ワシントンにある記者研修組織ICFJ(International Center for Journalists)とハワイ大学東西センターとの協力プロジェクト。1970年、両国報道機関の編集最高幹部がハワイで第1回日米編集者会議を開催した際、折からの日米繊維戦争などを機に認識された日米間の情報ギャップを埋めるため、両国間の相互理解促進を目指し、提案されたもの。 アメリカ側参加者は写真左側から次のとおり。 Ms. Linda FELDMANN, Opinion Page Editor, The Christian Science Monitor Topics.......Topics.......Topics........
|
|||||||||||||||||
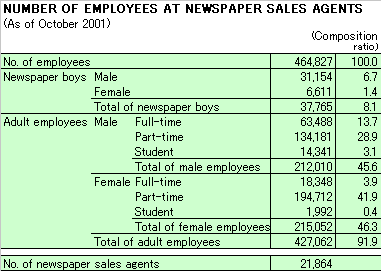
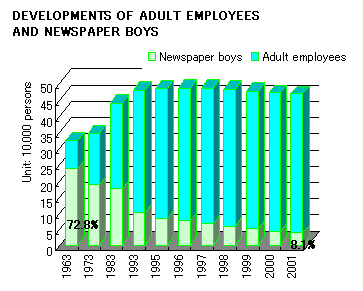


 新聞協会の2001年度日米記者交換計画で米国記者団のメンバー6人(写真)が2月13日来日、27日の離日まで、各界要人への取材や、沖縄、京都の視察など精力的にスケジュールをこなした。
新聞協会の2001年度日米記者交換計画で米国記者団のメンバー6人(写真)が2月13日来日、27日の離日まで、各界要人への取材や、沖縄、京都の視察など精力的にスケジュールをこなした。 2月8日から24日まで米ソルトレークシティーで開催された冬季五輪に新聞記者が選手として参加、話題を集めた。そり競技「女子スケルトン」の日本代表になった信濃毎日新聞社文化部の中山英子記者(31=写真・共同提供)は、20日の試合で12位の成績を残し、ソルトレークシティーを去った。
2月8日から24日まで米ソルトレークシティーで開催された冬季五輪に新聞記者が選手として参加、話題を集めた。そり競技「女子スケルトン」の日本代表になった信濃毎日新聞社文化部の中山英子記者(31=写真・共同提供)は、20日の試合で12位の成績を残し、ソルトレークシティーを去った。