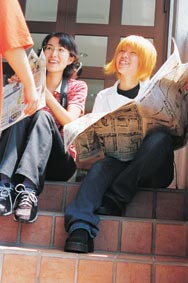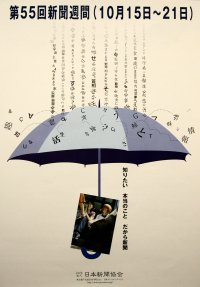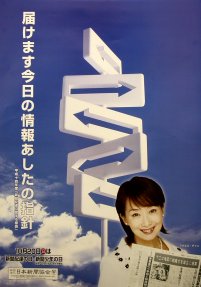|
NSK ニュースブレチン オンライン ------------------------------------------------------------------- 新聞協会はこのほど、2001年度の新聞事業の経営動向に関する調査結果をまとめた。売上高は前年度比2.5%減の1兆9897億7000万円、営業費用は1.5%減の1兆8928億0300万円で、営業利益は19.0%減の969億6700万円。販売収入は微増だったものの、広告収入の激減により、3年ぶりの減収減益となった。 調査は新聞協会加盟の日刊新聞112紙のうち大・中規模社42社を固定サンプルとして2001年度の決算を集計している。新聞協会全会員社を対象とした売上高推計調査によれば2001年の売り上げ推計は2兆4900億円なので、経営動向調査の対象社42社が新聞業界全体のほぼ80%を売り上げていることになる。 売上高を見ると、販売収入は前年度比0.1%増の1兆295億8800万円で、3年ぶりにわずかながら増率に転じた。広告収入は好調だった前年度から一転し、前年度比7.1%減の7108億9000円。すべてのクラスで減少した。減少率は部数の多い社ほど高かった。その他営業収入は0.7%増の2492億9300万円で、2年連続で増加した。 営業費用は1兆8928億0300万円で前年度比1.5%減。特に用紙費は5.1%減だった。用紙費と人件費はほとんどの社で減少した。 この結果、営業利益は前年度比19.0%減の、969億6700万円となった。経常利益は17.9%減の1003億8500万円、当期利益は22.1%減の417億2900万円となった。 日本新聞博物館(ニュースパーク、横浜市)主催の企画展「『海外邦字紙』と日系人社会」が1日、スタートした。海外日系新聞協会加盟紙を中心に世界の邦字紙約50紙を一堂に展示、約250万人の海外日系人社会の中で邦字紙が果たす役割に焦点を当てている。同企画展は12月23日まで開催される。海外日系新聞協会、海外日系人協会、外務省、国際協力事業団、横浜市が後援。
海外邦字紙の老舗のひとつにロサンゼルスで1903年に創刊された羅府新報がある。近代日本の移民政策によって海外に出て行った人々のためのメディアが海外邦字紙である。 期間中の11月3日には海外邦字紙の発行者、編集者らによるシンポジウム「海外邦字紙の歴史と今」を開催する。
日系人のための邦字紙に加えて、最近は仕事や留学、結婚などで海外に住む日本人を対象とした日本語メディアが元気だ。 海外日系新聞協会が昨年まとめた調査によれば、海外の日本語メディア80のうち、1990年以降出現したメディアは30。アジア、オセアニア、ヨーロッパでの創刊が盛んで、スポーツ、音楽、芸能ニュースを扱うメディアが増えた。無代紙も多い。
|
 同企画展では、1868年に海外移民が始まって以来、北米、ハワイ、中南米などの移住地で誕生した邦字紙の沿革、創刊号や最近の紙面を紹介。また、移住当時の生活を伝える写真や、戦後の日本で起きた大事件を報じた紙面なども展示している。
同企画展では、1868年に海外移民が始まって以来、北米、ハワイ、中南米などの移住地で誕生した邦字紙の沿革、創刊号や最近の紙面を紹介。また、移住当時の生活を伝える写真や、戦後の日本で起きた大事件を報じた紙面なども展示している。