NSK ニュースブレチン オンライン -------------------------------------------------------------------
今年で第55回を迎えた新聞大会は16、17の両日、愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催された。新聞協会賞の授賞式が行われた後、ノーベル化学賞を受賞した野依良治名古屋大学大学院教授が「21世紀の『知』とは」をテーマに基調講演、午後の研究座談会では坂村健・東京大大学院情報学環教授が「ユビキタス・コンピューティングが開く未来」をテーマに講演したほか、読売、日経、産経、北海道、中日の新聞社5社の経営幹部が「新聞商品の魅力を高めるために」をテーマに討論した。 討論では、「若い世代の間で新聞を読まない人が増えている現実を直視すべきだ」「新聞を読むことが知的な大人であることの指標でなくなってきている」など、最近の新聞離れに危機感が示された。これに対し、「新聞を商品として捕らえることに抵抗を感じるような意識を取り払い、商品改良に努めるべきだ」「信頼度を高めるためには、記者教育が重要だ」「地域に密着した読者サービスを進める」「すべての面において個々の新聞社が独自の個性を発揮する」「広告もニュースという原点に立ち返り、新聞にしかできない広告分野を開拓すべきだ」などの意見が出された。またデジタル化については、当面は紙の新聞とウエブサイトによる並存状況が続く見通しが述べられた。 新聞大会関連のイベントしては、名古屋市で「新聞写真コンテスト」の入賞作品が展示された。また、16日から5日間「Read Me. PLAZA in 名古屋」を開催、名古屋市内4か所でさまざまな催しを行った。東京、大阪、名古屋、福岡では読者を招待して「記念の集い」が開かれた。 毎年10月20日に定められた「新聞広告の日」の式典は、今年は20日が日曜日にあたるため、18日に東京・千代田区のパレスホテルで式典を行い、新聞広告賞の授賞式が行われた。「新聞配達の日」と「新聞少年の日」(10月20日)には、全国で新聞配達従業員や新聞少年・少女を慰労するための行事が行われた。
国交正常化後の1966年以来39回目を数える日韓編集セミナーが10月30日、東京・内幸町のプレスセンターホールで開催された。韓国側から15社15人、日本側から12社13人の報道関係者が参加し、「サッカーワールドカップ(W杯)共催後の日韓関係--今後の北東アジア情勢を中心に」をテーマに、最近の日本と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の国交正常化交渉、拉致問題なども踏まえた活発な議論が交わされた。韓国側から金泰翼(KIM Tae lk)朝鮮日報文化部長、日本側から山本勇二・東京新聞外報部部次長が基調報告した後、自由討議を行った。
また、W杯の韓日共催は韓国に「開かれた民族主義」を出現させたと指摘。「韓国の伝統的な民族主義は、被支配の経験から由来した閉鎖的なもので、韓日関係の進展にも障害となっていた。しかし、今日の新民族主義は、W杯で若者が国旗をマントのようにまとうなど遊戯精神とも融合した自発的なものに変化した。これからの韓日関係を新しく率いる重要な力になる」と力説した。 さらに、韓国で邦画「ラブレター」が大ヒットしたことを挙げ、「一人ひとりが相手側の具体的事項の一つ一つに、理解と愛情を持ち、そこから感動とヒューマニズムを見いだす努力をする時、韓日関係はさらに進展する」と結んだ。 山本氏は、W杯共催の成果として日韓の相互理解の深まりについて、「金大中政権が日本の大衆文化を段階的に開放した影響も大きい。特に若い世代の交流が重要であり、記者は日韓双方の社会、文化の面白さと魅力を伝える義務がある」と話した。 また、歴史教科書の問題に言及。「日本の教科書の内容に問題があるとの批判はあってもいい。しかし、駐日大使の一時召還や多方面における日韓交流事業の一時中止などといった外交圧力を強める方法には疑問が残る。正しい歴史認識を求める一方で、表現の自由を認める寛容さを持ってほしい」と提言した。 教科書問題については、午後の自由討議で、李基昶(リー・キ・チャン)韓国日報編集副局長兼体育部長が「歴史教科書の記述では、若い世代に真実を伝えることが重要であり、表現の自由を優先させるべき問題ではない」との指摘に対し、山本氏が「両国の教科書の種類や記述されている内容の幅の違いをお互いに理解することが、共同研究のきっかけとなる」と応えた。 このほか、「韓国には、様々な分野で日本の大学院学位をとった若手の知識人が大勢いる。彼らの中には職につけない者も多い。韓国と日本の橋渡しができる人材を活用する場の確保が必要だ。双方が相手国を学ぶための動機を提案するのもメディアの役割だ」(大澤文護・毎日新聞東京本社外信部副部長)との意見が出された。 日朝の国交正常化交渉に関しては、安相倫(アン・サンユン)ソウル放送解説委員は「日本は北朝鮮のコミュニケーションの取り方に慣れる必要がある。彼らは局面転換を図るとき、レトリックを駆使して劇的効果を狙う。拉致や核問題であっさり真実を認めたのは、日本と対話を持ちたいとの意思の表れだ。その根源には北朝鮮の厳しい経済状況がある」と話した。日本側からは、北朝鮮が国際社会での話法を理解することも必要だとの発言もあった。 菅原紀夫・北海道新聞東京支社国際部長兼論説委員は「小泉純一郎首相の訪朝に関するホワイトハウスの声明は、同盟国でありながら支援ではなく評価にとどまっている。日本の外務省は、北朝鮮の核問題に米国がこれほど敏感とは考えていなかった。日本も北朝鮮も米国の出方を読み誤っていると感じる」と言及。李光埴(リー・クワン・シク)江原道民日報論説委員からは、「北朝鮮が核保有を発想したとしても、攻撃のためではなく、米国の攻撃を阻止するためだ。中長期的には平和的解決は可能と考える」といった意見が出された。 自由討議の後、矢野哲郎・外務副大臣をゲストに招き、日朝正常化交渉への外務省の対応などについて意見交換した。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

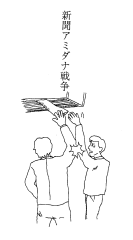

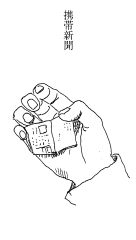




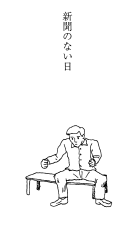
 金氏は、サッカーW杯後に韓国で起きた変化の一つとして、日本の植民地支配から解放された8月15日と、日韓併合で植民地支配の始まった8月29日の紙面展開を取り上げ、「これらの記念日には、日本の残忍性や、朝鮮民衆がいかに支配に立ち向かったかを大きく取り上げるとの不文律が韓国のマスコミには存在していた。しかし、今年の記念日に朝鮮日報は、民族の情緒に訴える記事は掲載しなかった。さらに重要なのは、読者からの抗議もなかったという事実だ」と話した。
金氏は、サッカーW杯後に韓国で起きた変化の一つとして、日本の植民地支配から解放された8月15日と、日韓併合で植民地支配の始まった8月29日の紙面展開を取り上げ、「これらの記念日には、日本の残忍性や、朝鮮民衆がいかに支配に立ち向かったかを大きく取り上げるとの不文律が韓国のマスコミには存在していた。しかし、今年の記念日に朝鮮日報は、民族の情緒に訴える記事は掲載しなかった。さらに重要なのは、読者からの抗議もなかったという事実だ」と話した。
