|
NSK ニュースブレチン オンライン
2003年11月 -------------------------------------------------------------------
*Topics
今月の話題>>> 新聞大会研究座談会、「今日の新聞、明日の読者」で討議 -------------------------------------------------------------------
続いて「激しく移り動く時代の中で、不安と緊張が世界に広がっている。新聞は報道機関の中核として、正確かつ迅速な報道と自由で責任ある言論により読者・国民の信頼にこたえ、安全で希望のもてる社会の構築に寄与しなくてはならない。第五十六回新聞大会にあたり、われわれ新聞人は、新聞のさらなる可能性を追求し、使命の達成に力を注ぐことを誓う」との大会決議を採択した。 午後の研究座談会では、新聞・通信五社の編集幹部が「今日の新聞 明日の読者」をテーマに討論が行われた。 衆院は10月10日に解散された。2002年春の国会以来継続審議となっていた人権擁護法案は廃案となった。法務省は、社会情勢の変化や人権問題に関する新聞・放送界の自主的な取り組みを踏まえ、一定の修正を検討した上で再度の国会提出を目指す。 02年3月、政府は人権侵害の類型として、「差別」「虐待」「公権力による人権侵害」に「マスメディアによる人権侵害」を加えた人権擁護法案を国会に提出した。 法案は「人権擁護に関する施策の総合的推進」を目的に、国家行政法に基づく「人権委員会」を法務省の外局として設置。救済手続きとして助言、指導などを行う「一般救済」に加え、調停や停止勧告などができる「特別救済」を設け、後者の対象に、報道機関による人権侵害を含めた。 犯罪被害者と家族、加害少年らのプライバシー侵害や「つきまとい、待ち伏せ、見張り、電話をする、ファクスを送る」などを繰り返す取材が報道機関による人権侵害の類型として挙げられた。 これに報道界は一斉に反発。新聞協会、民放連、NHKは02年3月7日、「政府機関による報道への不当な干渉につながりかねず容認できない」とする共同声明を政府に提出。新聞協会は同年4月にも、個人情報保護法案とともに人権擁護法案に断固反対する緊急声明を発表した。 同法案は、人権委員会を入国管理や矯正施設を所管する法務省の外局と位置付けたことも強い批判を受けた。 法務省幹部は廃案について「国会では、審議の結果否決されたわけではないので、あくまで再提出を目指して努力する。ただしこれまでの経緯から、同じ法案を再提出しても成立の見込みは乏しい」と述べた上で、「新聞や放送界が、人権侵害の回避に前向きに自主的取り組みを進めたことは認識している。そうしたことも踏まえて総合的に勘案し、いつ、どういった内容で再提出するのかを検討したい」と話している。 毎日新聞社は10月1日、ギリシャにアテネ支局を開設した。来年八月開催のアテネ五輪に向け、現地のさまざまな動きを伝える。 臨時支局のため体制は流動的だが、近く特派員を派遣する。これにより、毎日の海外の取材拠点は27となった。 アテネには毎日のほか、朝日新聞社、読売新聞社、産経新聞社、共同通信社が支局を開設しているほか、NHKが駐在員を置いている。
|
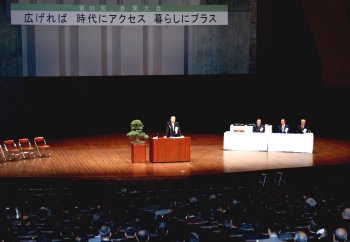 新聞協会は10月15,16日熊本市で第56回新聞大会を開催した。新聞協会加盟社幹部ら507人が参加した。初日の大会式典では、箱島信一会長(朝日新聞社代表取締役社長)が「言論・報道の自由とメディアの独立を脅かす報道規制の動きには、今後とも監視を続け、場合によってはこれを阻止するため闘う覚悟も必要だ」「情報や記事がコンテンツと言い換えられ、伝達ツールが紙だけでなく電波や電子媒体などへと多様化することはあっても、その中核は常に新聞業界が担っていくことに変わりはない」などと表明。
新聞協会は10月15,16日熊本市で第56回新聞大会を開催した。新聞協会加盟社幹部ら507人が参加した。初日の大会式典では、箱島信一会長(朝日新聞社代表取締役社長)が「言論・報道の自由とメディアの独立を脅かす報道規制の動きには、今後とも監視を続け、場合によってはこれを阻止するため闘う覚悟も必要だ」「情報や記事がコンテンツと言い換えられ、伝達ツールが紙だけでなく電波や電子媒体などへと多様化することはあっても、その中核は常に新聞業界が担っていくことに変わりはない」などと表明。
