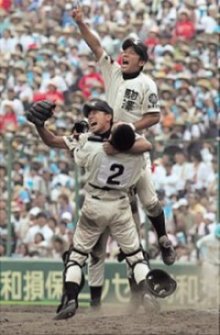|
NSK ニュースブレチン オンライン
2004年12月 -------------------------------------------------------------------
*Topics
今月の話題>>> 新聞社論説責任者懇談会――テーマは「米大統領選挙と日米関係」「郵政事業民営化」「三位一体改革と義務教育」 ------------------------------------------------------------------- 欧州連合(EU)の駐日欧州委員会代表部は10月29日、「日本の規制改革に関するEU優先提案」(EU提案)を外務省に提出した。2002年10月および03年10月の提案に盛り込まれていた記者クラブ制度の撤廃要求は今回、削除された。新聞協会は今年3月、各記者クラブに対し、外務省発行記者証を持つ外国報道機関記者の公式記者会見への参加を認めるよう要請していた。 昨年、一昨年の提案でEU側は、記者クラブ制度は外国報道機関の取材を妨げ、日本と欧州の情報の自由貿易を抑制しているほか、日本に関する情報を受け取る国内外の人々に大きなマイナスをもたらしているなどと指摘。(1)外国報道機関特派員に発行されている外務省記者証を、日本の公的機関が主催する報道行事への参加許可証として認め、国内記者と平等の立場でのアクセスを可能にする(2)記者クラブ制度を廃止することにより、情報の自由貿易にかかわる制限を取り除く――ことを外務省に提案した。 新聞協会では、編集委員会の下部組織・記者クラブ問題検討小委員会で、2002年11月から検討を始めた。03年12月には「記者クラブ制度は『知る権利』の代行機関として十分有効に機能しており、廃止する必要は全くない」などとする見解を発表。その一方で、04年3月には、外務省記者証を持つ記者の公式記者会見への参加を認めるよう全国各地の記者クラブに要請した。併せて外務省も、各省庁などの報道担当部局に対し、同記者証を持つ記者のオンレコ会見参加について必要な対応をとるよう求めた。 EU側は「制度廃止が趣旨ではない。記者のアクセスを除外する記者クラブの在り方を改めてほしい」「新聞協会の要請に効果が見られれば、記者クラブ制度廃止の提案は取り下げることになるだろう」などの考えを示していた。 最高裁が被害者の訂正放送請求を棄却――NHKのテレビ番組めぐる訴訟 NHKが放送したテレビ番組をめぐって、埼玉県の女性が離婚原因に関する真実でない放送で名誉を傷つけられたなどとして、NHKに放送法に基づく訂正放送や計410万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が11月25日、最高裁であった。最高裁は、「被害者は、放送事業者に対し、訂正放送等を求める私法上の権利を有しない」との初判断を示し、2審・東京高裁判決(2001年7月)のうち、訂正放送を命じた部分を破棄、女性側の請求を棄却した。 一方で、NHKの名誉棄損、プライバシー侵害は認定。女性側への計130万円の支払い命令が確定した。NHKは判決の翌26日、問題となった番組の中で判決内容を伝え、自主的に当時の放送内容を訂正した。 問題となった番組は1996年6月に総合テレビで放送。「妻からの離縁状・突然の別れに戸惑う夫たち」と題する放送の中で、女性の元夫が素顔で出演し、離婚の経緯などを語った。女性側は、「取材もないまま、虚偽の事実を放送され名誉を棄損された」「知人などに離婚の経緯等が知られ、プライバシーが侵害された」などと主張していた。 1審・東京地裁(98年11月)は女性側の訴えを棄却したが、2審は「NHKは、放送によって関係当事者が特定されないような方法をとるか、双方からの取材を尽くし真実の把握に努めるべきだった」などとして、賠償請求を一部認めた。また、番組中に訂正文を2回読みあげるよう、訂正放送を初めて命じていた。 最高裁では、真実でない事項の放送について被害者から請求があった場合に、放送事業者に訂正放送等を義務付けている放送法4条1項をどう解釈するかが争点となった。2審は、「被害者が私法上の権利として、訂正放送を求めることができることを規定したものと解するのが相当」と判断していた。 最高裁は判決の中で、「表現の自由の保障の下において、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図る」こととし、同項を「放送の自律性の保障の理念を踏まえた上で、真実性の保障の理念を具体化するための規定と解される」と判断。同項義務違反について罰則が定められていることなども併せ考えると、「同項は、表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体への公法上の義務として定めたものだ。被害者からの請求は、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けている」との判断を示した。 損害賠償に関する上告については今年7月、上告を受理しない決定がされており事実上確定していた。 女性側は、訂正放送と併せて、民法723条(名誉棄損に関する原状回復)に基づく謝罪放送も請求していた。しかし、2審は「損害賠償に加え、訂正放送で名誉は回復されるため必要ない」と退けたため、NHK側から不服申し立てがなされず、最高裁の審理判断対象にはなっていなかった。 NHK広報局は11月25日、「訂正放送の請求が棄却されたことについては、主張が認められたものと考えている。名誉棄損、プライバシー侵害については、主張が認められなかったことを真摯に受け止め、自主的に訂正放送をするかどうか検討する」とのコメントを発表。翌26日の同番組中で約5分間にわたり、アナウンサーが判決内容を伝えた上で、当時の放送内容と事実との差異を説明、訂正した。 女性側弁護団は、「自律性保障の観点から、刑事罰があるなどの理由も併せ、私法上の訂正放送の請求権がないとしているが、自律的というのであれば、刑事罰の発動も望ましくないことになる。民事上の解決ではなく、刑事告訴しろと言っているに等しい。表現の自由への制約は極力避けるべきだが、釈然としない。自主的な訂正放送は評価するが、内容は放送当時でもすぐに分かったことで提訴から9年後では遅すぎる」と話している。
|
||||||||||||||||