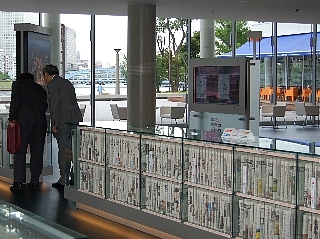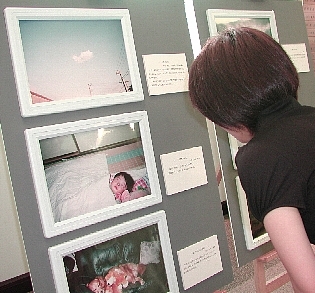|
NSK ニュースブレチン オンライン
2007年8月 -------------------------------------------------------------------
*Topics
今月の話題>>> 盲学校生の写真展――ニュースパーク ------------------------------------------------------------------- 7月16日午前10時13分ごろ、新潟県柏崎市、長岡市、長野県飯綱町(いいづなまち)などで震度6強を記録する地震が起きた。この地震は「新潟県中越沖地震」と名付けら、22日午後9時現在、死者10人、負傷者1842人にまで拡大した。地元紙の新潟日報や全国紙など新聞各社は、被害の状況を克明に伝え、生活情報欄を特設し詳細なライフライン情報を提供。緊急停止命令を受けた柏崎刈羽原子力発電所の耐震性や東京電力の対応なども検証する。読売は広報宣伝車を使い、柏崎市で「応援号外」を発行した。 17日付朝刊では2ページを「生活関連情報」に充て、ライフラインや病院、金融機関などの情報を掲載した。この日から連日、生活情報のページを設ける。同社の竹内希六(たけうち・きろく)取締役編集担当編集局長は「04年の中越地震の際、読者が一番知りたいのは生活情報だと身に染みて感じた。地震直後から情報提供に努めている」と話す。 インターネットでも16日から、ブログ形式で災害情報を随時、更新して伝えた。市民からも被災地の情報を電子メールで受け付け掲載した。05年末の豪雪時以来の取り組み。同社情報文化センターは「緊急災害時に役立つメディアとして、今後もこうしたツールを活用していきたい」としている。 全国紙も被災地の生活関連情報の提供に努めた。朝日は「中越沖地震 ライフラインの状況」「くらし応援します」などの見出しで情報欄を掲載。毎日も「サポート情報」の欄を設けた。 読売は「震災掲示板」欄を特設した。関連地域の主要鉄道の路線図と道路図を掲載し、不通区間などを図示する。大きな被害を受けた柏崎市には17日、東京本社の広報宣伝車を派遣。川越工場で印刷した夕刊100部を避難所配布した。20日には、現地のボランティアによる被災者への激励を集めた「応援号外」を制作し、避難所などで3000部配布した。広報部員が現地で取材し、B4判1ページにまとめた。同社広報部では「被災者のために何ができるかを考え、社会貢献として取り組んだ」と話している。 今回の地震では、柏崎市と刈羽村にまたがる柏崎刈羽原発で変圧器から出火、放射性物質を含む水の流出などが発生した。緊急停止命令が柏崎市から出された。原発沖の活断層は、今回の地震の震源になったとも指摘されている。しかし、原発の設計には考慮されず、耐震性の確保に疑問が投げかけられた。 各紙とも、この問題の検証を進める。新潟の竹内氏は「原発の安全性が改めて問われている。生活の安心・安全の根幹にかかわる問題ととらえ、報道に力を入れる」と語った。 (写真あり・キャプション:避難所となっている柏崎小学校で地震の被害を伝える朝刊を読む被災者=17日午後:新潟日報社提供)
第12回NIE全国大会は7月26、27の両日、「学びあい 世界を広げるNIE」を掲げ、岡山市の岡山コンベンションセンターで開かれ、全国から教育・新聞関係者ら約850人が参加した。文部科学省などが後援した。初日のパネルディスカッションで、高校生から「NIEで視野が広がった」との感想が出された。また、学校全体での取り組みには管理職がNIEへの理解を深めることが課題に挙げられた。2日目は、小中高の校種別に実践発表などが行われた。 続いて地元出身の作家で、教員免許も持つ重松清(しげまつ・きよし)氏が記念講演した。「若い世代は自分にとってあこがれの人を探したい欲求が強い」とスポーツ紙を活用したNIEで「ヒーロー探し」を提案した。 影山氏は、学校への記者派遣の経験から「子供たちは、情報には送り手がいることを学べたと思う」と話した。自身も、責任の重さなど学ぶことが多かったという。冨谷さんは理科の授業で新聞を活用した感想を「考えが深まり視野も広がった」と述べた。 横田氏は今後の課題に、小中高の連携や管理職の理解を挙げた。 前田氏は、記者に授業への助言を求めたいとする教師の要望も多いとして「記者派遣以外にも、学校との連携は可能か」と質問。影山氏は「要望があれば、コミュニケーションを強化したい」と応じた。 (写真あり:キャプション:パネルディスカッションでは、NIEの魅力を教師、高校生、新聞記者らが語り合った=7月26日、岡山市の岡山コンベンションセンター)
新聞社の従業員数は全体で前年比2.6%減少、定年後再雇用が増加 新聞協会はこのほど、協会加盟の新聞・通信102社を対象に実施した2007年「従業員数・労務構成調査」結果をまとめた。102社の従業員総数は15年連続で減少し、前年比2・6%減の5,0911人だった。減少が始まった1993年以降では、05年の3・2%減に次ぐ減率幅(表1参照)。定年後の再雇用者数が大幅に増え、60歳以上の比率は0・6ポイント拡大した。 【従業員総数】 1992年をピークに減少が続く。98年からの10年では1万133人減少した。一方、女性は0・3%増加した。 表1 従業員総数の推移 〈△=減〉
(注)新聞協会加盟の新聞・通信全社(07年は102社)を対象に集計 【部門別従業員数・構成】(表2参照) 部門別の従業員数がわかる詳細な回答を寄せた80社の従業員総数は48,069人で、人数が最も多い部門は「編集」(構成比で0・9ポイント拡大)の48・8%。以下、「営業」(同0・3ポイント縮小)、「その他」(同1・2ポイント拡大)「製作・印刷・発送」(同1・2ポイント縮小)、「統括・管理」(同0・1ポイント縮小)、「出版・事業・電子メディア」(同0・6ポイント縮小)の順で続く。 6年連続で構成比が拡大していた「営業」が縮小に転じたほか、「その他」が「製作・印刷・発送」を上回った。 10年間の推移では、「編集」が7・4ポイント拡大した一方、「製作・印刷・発送」が13・0ポイント縮小した。 「編集」のうち、記者の総数は19,124人となり、7年ぶりに2万人を割り込んだ。女性記者は2631人で、構成比は記者総数の13・8%。前年より1・1ポイント拡大した。 表2 部門別従業員数・構成(80社)
【年齢段階別従業員構成】(表3参照) 「55〜59歳」が最も多い。ただし、構成比は0・9ポイント縮小した。以下、「50〜54歳」「35〜39歳」「30〜34歳」と続く。20代以下と50代は縮小傾向が続いている。 この10年で最も拡大した世代は40代で4・0ポイント増。次いで30代の3・0ポイント増。20代以下は5・7ポイント縮小した。 表3 年齢段階別従業員構成比率の推移(単位:%)
【採用・退職状況】(表4参照) 2006年4月2日から1年間の新規採用者数は、男性923人(構成比68・2%)、女性431人(同31・8%)。年間採用率(在籍従業員に占める新規採用者の割合)は2・8%となり、前年から0・3ポイント増加した。 一方、年間退職率(在籍従業員に占める退職者の割合)は、4・6%となり、前年から0・1ポイント増加した。
表4 新規採用者数と退職者数の推移
【定年後再雇用者】 男性1269人、女性31人の計1300人。06年4月2日から1年間の再雇用者数は530人となり、昨年の288人から大幅に増加した。部門別では「編集」が237人と最も多い。 新聞協会は、11月6日から4日間、第19回新聞製作技術展(JANPS2007)を東京・有明の東京国際展示場(東京ビッグサイト)で開催(主催)する。日本新聞製作技術懇話会(CONPT:Conference for Newspaper Production Technique-Japan)が協賛。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||