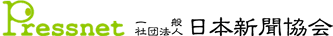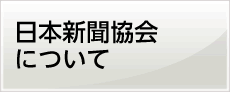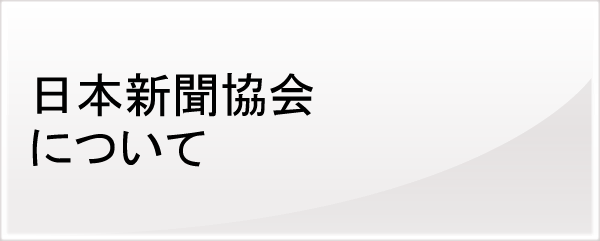- 日本新聞協会トップページ
- 日本新聞協会について
- 役員・定款
定款
1946(昭和21)年7月23日制定
1998(平成10)年3月2日改正認可
第1章 総則
第1条 この法人は、社団法人日本新聞協会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区内幸町2丁目2番1号に置く。
第3条 この法人は、必要の地に支部を置くことができる。
第2章 目的
第4条 この法人は、全国新聞、通信、放送の倫理水準を向上し、共通の利益を擁護することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 新聞倫理の高揚と新聞教育の普及
- 新聞、通信、放送に関する調査研究
- 新聞、通信、放送の諸問題に関する内外との連絡
- 会報および資料の発行
- その他理事会で必要と認めた事項
第3章 会員
第6条 この法人の会員は、この法人が制定する新聞倫理綱領を守ることを約束する新聞、通信および放送事
業を行う者で、別に定める定款施行細則(以下「細則」という)所定の入会手続きを経て、理事会が承認した者とする。
第7条 この法人の会員となろうとする者は、細則に定める方式にもとづき申し込むものとする。
前項の申し込みにあたっては、会員となる者を代表して、この法人に対する権利、義務を行う者(以下「代表者」という)1名を定めて申し込むものとする。ただし、代表者は、会員となる者の役員でなければならない。
代表者が会員である者の役員の資格を喪失した場合には、その資格を喪失するものとする。
会員が、その代表者を変更したときは、すみやかに届け出なければならない。
第8条 前条の申し込みをした者で、入会の承認通知を受けたものはその通知受領後2週間以内に入会金および当月分会費分担金を納入しなければならない。
会員の資格は、前項の入会金および会費分担金を納入したときから生ずるものとする。
第9条 入会金は金80万円とし、会費分担金は、理事会で定めた基準による。
会員は、毎月会費分担金を納入しなければならない。
いったん納入した入会金および会費分担金は、いかなる理由があっても、これを返還しない。
第10条 会員がこの法人の目的に違反する行為をしたときは、理事総員の3分の2以上の同意をもって除名または6か月を越えない期間を定め権限の一部を停止(以下「権限の一部停止」という)することができる。
この場合、停止期間中であっても会費納入の義務は履行しなければならない。
会員が会費分担金の納入を3月以上怠ったときは、理事会の議決を得て除名することができる。
第11条 この定款に定めてある事項のほか会員の入退会に関する手続きおよび方法は、別に細則において定める。
第4章 役員
第12条 この法人は、次の役員を置く。
- 理事 35名以上45名以内
- 監事 3名以上5名以内
理事のうちに会長1名を置き、副会長3名以内、専務理事1名を置くことができる。
第13条 理事および監事は、会員総会(以下「総会」という)において代表者のうちから選任する。
前項の規定にかかわらず、総会は専務理事となる者1名を理事に選任することができる。ただし、専務理事を置かないときは事務局長を理事に選任することができる。また、会長に選任された代表者を有する会員である者の役員のうちから1名を理事に選任することができる。
会長、副会長および専務理事は理事の互選により定め、総会の承認をうけるものとする。
第14条 理事および監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
会長、副会長、専務理事の任期は理事の任期と同一とする。
補欠または増員により就任した役員の任期は、前任者または現在同職者の残余期間とする。
理事および監事の任期が、定款によって開かれる総会前に到来するときは、第1項の規定にかかわらず任期満了後最初に開かれる総会までその任期を延長する。
第15条 代表者がこの法人の役員である場合に代表者としての資格を喪失したときは、この法人の役員の資格を失う。
この法人の役員が、前項によりその資格を失ったとき、または役員を辞任したときは、会長は理事会の承認を得てその役員の属した会員の後任代表者を補欠役員とすることができる。
理事である事務局長が退任したときは、会長は理事会の承認を得てその後任者を補欠理事とすることができる。
会長に選任された代表者を有する会員から選任された理事は、会長が退任したときは退任するものとする。
第1項の規定は、会員が退会、除名または権限の一部停止の場合にこれを準用する。
前項、権限の一部停止により退任した役員については、第13条第1項の規定にかかわらず停止期間経過後、理事会において理事総員の3分の2以上の同意をもって前職に選任することができる。
第16条 会長は、この法人の会務を総理し、この法人を代表する。
会長は、理事会を招集し、その議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定した順位にしたがいその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
専務理事は会長の命を受けて常務を処理する。
第17条 この法人の各業務について会長が必要と認めたときは、理事のうちからその部門に関する担当者を指名することができる。
第18条 理事は、理事会を組織しつぎの事項を議決するとともに定款および細則において定める事項を審議決定する。
- 細則の制定変更および廃止
- 予算および決算
- 会員の入退会および除名
- 前各号のほか会長が必要と認めて付議した事項
第19条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
- 法人の財産の状況を監査すること
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- 財産の状況または業務の執行に不正の事実を発見したときは、これを理事会および総会または文部科学大臣に報告すること
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること
第5章 会議
第20条 総会は、毎年1回会長が招集する。
総会の招集は、少なくとも10日前に、その会議の目的とする事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
会員総数の過半数の同意あるときは、あらかじめ通知しない事項についても決議することができる。
第21条 総会における会員の表決権は、各1票とする。
会員の代表者は、その会員所属の役職員または他の会員の代表者に書面で委任しその表決権を行使することができる。
第22条 総会の議長は、会長とする。
総会は、定款に別段の定めがある場合を除くほか会員総数の過半数の出席をもって成立する。
総会の議事は、出席表決権の過半数で決し可否同数のときは、議長が決するものとする。
第23条 理事会における理事の表決権は各1票とする。
理事会は、理事総数の過半数の出席をもって成立し、その議決は3分の2以上の同意を要する。
ただし、細則の制定、変更および廃止には、理事総員の4分の3以上の出席を要する。
第24条 理事の代理者は、次の者に限る。
- その理事の属する会員である者の役員であって、1名を限り当該理事就任の際に届け出を行い、理事会の承認を得た者
- 理事または代理者であって、書面により表決権の行使を委任された者
第25条 次の事項は総会に報告するものとする。
- 細則の制定変更および廃止
- 予算および決算
- 会員の入退会および除名
- 前各号のほか会長が必要と認めた事項
第6章 委員会
第26条 この法人は、事業遂行上必要に応じ委員会を設ける。
第27条 委員は、会員である者の役職員から会長これを委嘱する。
ただし、会長は、必要に応じ理事会にはかって会員と関係のない専門家を委嘱することができる。
第7章 顧問および参与
第28条 この法人に顧問および参与を置くことができる。
顧問は、この法人の事業遂行に関する事項の諮問に応ずる。参与はこの法人の事業遂行に関する専門事項の諮問に応ずる。
顧問および参与は学識経験者のうちから会長が理事会の承認を経て委嘱する。
顧問および参与の任期は理事会の承認を経て別に定める。
第8章 資産および会計
第29条 この法人の資産は、次のとおりである。
- 別紙財産目録記載の財産
- 寄付財産
- 入会金および会費分担金
- 事業に伴う収入
- その他の収入
第30条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入された資産で構成する。
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
ただし、寄付財産であって寄付者の指定あるものは、その指定に従う。
第31条 基本財産は、処分し、または担保に供してはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
第32条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
借入金(その会計年度内の収入をもってする一時借入金を除く)についても同様とする。
第33条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
第34条 会長は、毎年3月末日までに事業計画およびこれに伴う収支予算を、毎会計年度終了後3月以内に事業報告、収支決算および財産目録ならびに会員異動状況書を作成し、これを理事会および総会の議決を得て、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。
第9章 事務局
第35条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
第36条 事務局に事務局長1名および必要な職員を置く。
事務局長は会長および専務理事の命を受け事務局を総括する。
事務局長は理事会の承認を経て会長が任免する。
第10章 定款の変更ならびに解散
第37条 この定款は、理事会および総会において、それぞれ、その構成員の4分の3以上の同意による議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第38条 この法人の解散は、総会において会員現在総数の4分の3以上の同意による議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
第39条 この法人が解散したときは、会長または会長の指名したものが清算人となる。
第40条 清算の結果残余財産が生じたときは、清算人は、文部科学大臣の許可を得て、この法人と同種類の公益事業にこれを寄贈するものとする。
付則
第41条 この定款で規定した事項のほかこの定款の施行ならびにこの法人の運営について必要な事項は別に細則で定める。
【定款施行細則】
第1章 総則
第1条 この施行細則は、社団法人日本新聞協会定款の規定にもとづき制定する。
第2章 入退会
第2条 定款第6条の資格を有する者で、この法人に入会を希望する者は末尾「書式第1号」様式の入会申し込み書に「書式第2号」の様式による会員の代表者2名以上の入会依頼書および新聞・通信にあっては「書式第3号」放送にあっては「書式第4号」の参考資料を添付し申し込むものとする。
第3条 前条の申し込みがあったときは会長は下記の各号につき調査し、これに該当するものと認めたときはこれを理事会に上程する。
ただし第1号に該当しない場合でも会長が会員として適格であると認めたときはこれを理事会にはかることができる。
- 6か月以上業務を継続していること
- 新聞においては次の要件を備えるものとする。
- 一般時事または主としてスポーツに関するニュースを報道するものであること
- 紙面内容が新聞倫理綱領に合致し品位を保っていること
- 週6日以上発行するものであること
- 建てページは4ページ以上であること
- 発行部数は1万部以上であること
4.放送においては、一般時事に関するニュースを報道し、公共的性格を有すること
5.その他理事会が必要と認めた条件に合致すること
第4条 理事会は前条の調査結果にもとづき入会の諾否を決定する。
会長は、前項にもとづき入会の諾否決定を入会申し込み者に対し書面をもって通知する。
第5条 会員が退会しようとする場合はあらかじめその旨書面でこの法人に申し出、理事会の承認を得なければならない。
第6条 会長は、会員にして細則第3条の資格を喪失した者については理事会の承認を得て除名することができる。
第7条 会員にして業務を停止した場合も前条と同様の方法によって除名することができる。
第3章 会費納入
第8条 定款第9条に定める会費分担金の納入期限は、当月末日とする。
第4章 理事 待遇
第9条 会長は専務理事または事務局長を補佐するため理事会の承認を得て事務局に理事待遇者3名以内をおくことができる。
理事待遇者の任期は理事の任期と同一とする。
ただし、再任を妨げない。
付則
第10条 この細則は昭和58年6月22日から施行する。
ただし、同日現在この法人の会員で第3条の各号の内容を具備しない者でもひきつづきこの法人の会員としての資格を有する。(入会申し込み書式第1~4号省略)