|
NSK ニュースブレチン オンライン
2003年5月 -------------------------------------------------------------------
*Topics
今月の話題>>> インターネット事業の確立に向け有料化を模索――新聞各社 -------------------------------------------------------------------
昨年10月15日、北朝鮮から帰国した拉致被害者5人に対する取材は、依然代表取材を中心とした異常な事態が続いている。このため、自由な取材の実現を求めている新聞協会は5月1日、民間放送連盟とともに「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」および「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」と懇談した。 拉致被害者の取材については、在京社会部長会はじめ拉致被害者の出身地である新潟県、福井県の報道各社で、拉致被害者の帰国に際し、集団的過熱取材の発生を防ぐため「節度ある取材・報道」を申し合わせ、現在まで記者会見などは代表取材で対応している。一方で、代表取材では「肝心な点が聞けない」といった意見や、「拉致被害者への対応が取材規制の前例として利用される可能性がある」といった指摘もあり、直接取材の実現が課題となっている。 懇談を申し入れた際、新聞協会と民放連は、「拉致被害者が置かれた『微妙な立場』は十分に承知している。貴会の思いを謙虚に受け止め、『誤解』の壁を乗り越えて、『報道の在り方』を考えたい」と表明(2002年11月号参照)。 さらに(1)帰国当初の状況とは大きく変わり、被害者らは日本の暮らしになじみ、状況をきちんと理解するようになった、(2)北朝鮮に家族を残していることなどは理解するが、直接取材できないといった異常な取材制限が続いている、(3)現在の取材の在り方では、どのメディアも同じ内容の画一的な報道になり、報道機関に課せられた使命達成の支障となっている、(4)本人の真意が誤って伝えられる可能性も危ぐされる――などとあらためてと申し入れた。 これに対し家族会側は、懇談の中で(1)節度ある取材が維持されていることに感謝しており、メディアとは今後も良好な関係を続けていきたい、(2)個別取材は受けていないが記者会見での自由な質疑は既に実現している――などと強調した。 その上で、「帰国から半年が過ぎ、余裕が出てきたように見えるかも知れないが、5人はいまだに警察の事情聴取を受けていない。それは家族を北朝鮮に残しているからだ。家族が帰国して状況が大きく変わるまでは、『節度ある取材』を続けるよう、再度お願いする」「5人は国家的犯罪の被害者であるといった視点を忘れないでほしい」と説明した。 これに対し報道側は「5人は公人ではないが、5人の北朝鮮での暮らしぶりや、北朝鮮はどのような国なのかは国民の大きな関心事である。ぜひ肉声で語ってほしい。世論、政府を動かし問題解決につなげるためにも必要だ」と要望した。 拉致被害者への取材が制約される中で、3月中旬、拉致被害者の1人である曽我ひとみさんの日程を新潟県真野町が、偽って発表するといった事例も発生した。帰国以来、曽我さんの日程は曽我さんが在住する真野町の役場が本人に確認の上、報道機関に発表していたが、「終日、自宅で過ごす」と発表していた期間中、東京で肺ガンの摘出手術を受けていたことが判明したものだ。これに対し新潟県内の報道機関で構成する新潟県報道責任者会議は、「報道機関に対する完全な裏切り行為」だと抗議、真野町および極秘扱いを要求した政府とも新潟県責任者会議に謝罪したが、自由な取材が行われないことの危険性が改めて認識される事例となった。
今回の主なテーマは「日本の中小企業制度」。団員の一人、中国財経報(China Financial & Economic News)の姚中利(Yao Zhong-li)・副総編集(Vice Chief Editor)は日本の印象を「仕事に対する態度が非常にまじめで効率のいい国」と述べ、「低迷する日本経済だけでなく、歴史や文化にも興味があるので、いろいろ見て回りたい」と話した。 一行は、読売新聞東京本社の論説委員から日本の経済問題についてブリーフィングを受けたほか、中小企業庁や財務省、東京証券取引所などを訪問した。 その後、浜松、京都を経て岡山に移動し、岡山市の山陽新聞社を訪ね幹部と懇談した。この後、愛媛、大阪での視察を経て帰国した。 胡錦濤国家主席(党総書記)体制になった中国では、「報道改革」が加速している。政府が国内メディアに対して政府幹部の動向や会議の内容を過剰に報道せず、国民の関心に応じた内容を取り上げるよう求める方針を発表した。 これについて団長の汪発楷(Wang Fa Kai)・中国質量報(China Quality Daily)常務副総編集(Standing Vice Chief Editor)は、報道改革の目的を(1)生活情報(2)社会の動き(3)国民の考え――の3点を一般の人々に広く知らせることと説明。「改革は報道だけでなく、中国全体の発展につながっていく。多くの人に喜んでもらえるよう、各紙とも、記事内容の工夫や写真、グラフの活用など編集面での取り組みを以前から進めている」などと話していた。 Participants are: Wang Fakai(China Quality Daily / Standing Vice Chief Editor)
|

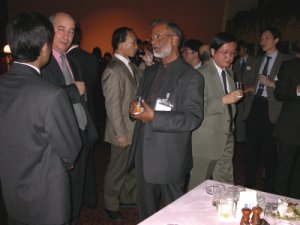 新聞協会が内外の報道関係者が懇親を深めることを目的に毎年開いている在日外国報道関係者招待レセプションが4月23日、東京のプレスセンタービル10階のレストラン・アラスカで開催された。
新聞協会が内外の報道関係者が懇親を深めることを目的に毎年開いている在日外国報道関係者招待レセプションが4月23日、東京のプレスセンタービル10階のレストラン・アラスカで開催された。