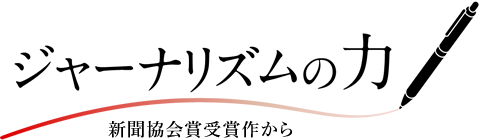2023.12.28
スポーツ指導に暴力不要 認識変える一歩に
柔道女子代表の暴力・パワーハラスメント問題のスクープ(2013年)
共同通信社・田村崇仁氏に聞く
共同通信社は2013年1月29日、柔道女子の日本代表を含むトップ選手15人が代表監督やコーチからパワーハラスメントを受けたとして日本オリンピック委員会(JOC)に文書で告発していたことを報じました。告発文の存在をつかみ、国内トップレベルの指導の場で暴力が振るわれ、隠蔽されていた事実を明らかにしました。全日本柔道連盟(全柔連)の不祥事が次々と明るみに出るきっかけにもなったスクープは、13年度の新聞協会賞を受賞。社会に大きな影響を与えたと評価されました。
スクープ当時、JOC・体協取材班のキャップを務めていた田村崇仁・現運動部デスクに、当時の報道の足跡や、スポーツ界での暴力指導を巡る10年間の変化、共同通信社での取り組みなどについて聞きました(インタビューは23年12月に実施しました)。
「暴力指導」巡る議論が活発に
柔道界で起こった暴力問題に関するスクープが、当時のスポーツ界や社会に与えた影響についてあらためてお聞かせください。

田村氏 この問題を報じる前年、大阪市立(現府立)桜宮高のバスケットボール部員が顧問から受けた体罰を苦に自殺する事件が発生しました。当時はスポーツと暴力的な指導の在り方が社会全体でクローズアップされていました。そうした中、上意下達で閉鎖的ともいわれる柔道界で女子の日本代表選手が結束して声を上げたことに、ただならぬ決意を感じました。一方、全柔連は選手の訴えを黙殺しているような状態でした。女性のトップ選手による集団での訴えは異例で、取材班の一人として堅いガードをこじ開けて報じなければ、選手の訴えは闇に葬り去られるかもしれない――。そう覚悟して出稿したことを覚えています。
反響は予想をはるかに超え、政府による暴力根絶に向けた取り組みが、第一報の後に本格化しました。下村博文文部科学相(当時)は13年2月に「日本のスポーツ史上最大の危機」との声明を発表。5月には運動部活動の指導ガイドライン(指針)を策定しました。指針には、許されない指導の具体例として、殴る・蹴るといった暴力行為に加え、暑い中でも水を飲ませないことや長時間にわたる無意味な正座などが盛り込まれました。
同年4月には、日本体育協会(現日本スポーツ協会)やJOCなど計5団体が「暴力行為根絶宣言」を採択しました。いわゆる「愛のむち」に疑問を持たない指導者に対し、「暴力は必要悪」という誤った考え方を捨てるよう求めた点は大きな一歩だったと思います。
暴力指導を巡る議論も活発化しました。当時の指導現場には根性論を引きずる風潮が残り、過去に自らが体罰指導を受けた経験から負の連鎖で選手に手を出す指導者もいました。そうした中、対話を重視する指導や選手の自主性を促す理論が必要だという声や、海外の指導法を紹介する動きなどが生まれ、社会のうねりにつながったと感じます。さまざまな視点に立った議論が増えたことが、体罰文化に歯止めをかける一助になったのであれば、報道の成果と言えるのではないでしょうか。
他方、メディアが暴力指導について見て見ぬふりをしてきた面があるとすれば選手の「勝利至上主義」を長年助長してきた点は否めません。報じる側の自省も必要だと考えています。
「言葉の暴力」は今も 指導現場の課題
特報から10年が経過しました。スポーツ協会が指導での暴力・暴言の撲滅を目指す「NO!スポハラ(スポーツ・ハラスメント)」活動を始めるなど、宣言採択から10年の節目に合わせた動きがみられます。一方で、選手が成長するために暴力をいとわないという風潮も残っているように感じます。今、スポーツ界の暴力指導に対する意識改革はどこまで進んだとお考えでしょうか。
田村氏 暴力根絶はまだ道半ばですが、スポーツ界は当時の報道をきっかけに、一歩ずつ着実に変わってきたと感じます。女性を含め、それまで表面化していなかった暴力やパワハラ被害を訴える選手が増えてきました。
女子柔道も変革と再生の道を歩んでいます。21年の東京五輪で、コーチ6人のうち4人は女性でした(12年ロンドン五輪では5人中2人)。こうした変化も、4階級を制覇した女子柔道の躍進に寄与したのではないかと捉えています。平手打ちや棒を振り回しての威嚇、「ブス」「ブタ」「死ね」「家畜と一緒」などの侮辱的発言があったことがJOCによる調査報告書(13年)で発覚しました。その後、暴力問題を契機に対話を重んじる組織を目指したことで、現場の記者からも「風通しが良くなった」との声を耳にします。
スポーツ協会は「NO!スポハラ」活動の一環で、ハラスメントに関するセミナーなどを選手の保護者対象に開いています。「成長のためなら子供がぶたれても構わない」と、暴力を振るう指導者になびいてしまう保護者も多いと聞きます。暴力に頼ろうとする指導者に対し、保護者が「NO!」と言える環境を築くためにも、こうした活動に取り組む意義は大きいと考えます。
同協会は23年4月、「暴力行為等相談窓口」に寄せられた22年度の相談が373件に上ったと発表しました。窓口を設けた14年度以降では過去最多の数字ですが、暴力に対する問題意識が高まったことで選手や第三者が声を上げやすくなったとも捉えられるのではないでしょうか。
相談内容を見ると、目に見える暴力行為は減った一方、全体の34%を「暴言」が占め最多となりました。選手の人格を否定する目に見えない「言葉の暴力」が増加傾向にあり、指導の「陰湿化」が問題の一つと言えます。また、被害者の約4割は小学生です。保護者に向けた啓発も重要だと感じます。
多角的な報道で模索する指導者の一助に
スポーツ界では、今も不適切な指導が根強く残る様子がうかがえます。体罰やハラスメント根絶に向け、メディアはどのような切り口で報じる姿勢が求められているのでしょうか。共同通信社の取り組みについても併せてお聞かせください。

田村氏 共同通信社は23年1月、運動部に暴力・パワハラ問題を扱うチームを組み、連載や企画の取材に着手しました。21年東京五輪・パラリンピック、22年北京冬季五輪・パラリンピックに出場した競技団体を対象に、宣言採択後の暴力やハラスメントに関する変化を尋ねるアンケート調査を実施。4月に結果を公表しました(https://nordot.app/1023203783654621184)。回答した56団体のうち、相談窓口を設置していると答えた団体は9割を超えました。このうち約7割で窓口の活用実績があることも分かりました。スポーツ界全体で相談体制の整備が進んだ点は、この10年の成果と言えるでしょう。
一方で、宣言採択後に「暴力問題は改善された」と答えた団体は5割弱にとどまりました。暴力行為がなくならない主な要因は、指導者の理解不足などにあると考えられます。暴力指導を繰り返す指導者の多くは、暴力やハラスメントにあまり関心を持っていません。彼らにアプローチし啓発することがメディアの役割の一つだと認識しています。
各競技団体の調査体制にも課題はあると考えます。団体の調査権限はどこまで認められるのか、匿名通報があった場合はどう対応すべきか――。試行錯誤しながら被害者のSOSに向き合う競技団体の実情を取り上げていくことも必要だと思います。
元バレーボール日本代表の益子直美さんが主催する「監督が怒ってはいけない」ことをルールとする大会など、新しい指導スタイルの確立に向けた取り組みも追っています。また、選手に対し暴力を振るった過去を持つ指導者が再起を図る様子を連載しました。
一方で、暴力被害に苦しむ選手側の声を伝えることには、取材に応じてもらうハードルの高さなどから難しさも感じています。ただ、閉鎖体質だったスポーツ界にも新たな動きがみられます。スポーツ協会は23年11月、柔道女子五輪金メダリストの谷本歩実さんら3人が暴力指導に対し声を上げる重要性を伝える動画を公開。このうち一人は動画内で10年前の暴力問題に言及し、「(告発した選手が)『NO!』と言えたことはとても大きい。自分のことだけでなく、将来を憂えていたのではないか」と話しました。告発した15人は今も非公表ですが、当時を知る元選手が、この問題で公に口を開くことはそれ以前にほとんどなかったようで、こうした動きが表れたことは大きな変化だと受け止めています。
10年前、体罰と叱咤激励の線引きをどうするのかと戸惑う声を多く聞きました。メディアが暴力の実態を報じても、指導体制が迅速に見直されるとは限りません。それでも、暴力指導を少しでも減らすために継続して伝えることが大切だと考えます。また、指導者自身もより良い指導法を求め、悩み続けています。メディアの多角的な視点の報道が、適切な指導の在り方を模索する一助になればと願っています。
<プロフィール>

田村 崇仁氏(たむら・たかひと)氏
共同通信社
運動部デスク
群馬県出身、早大卒。1996年入社。サッカー、プロ野球、日本オリンピック委員会(JOC)担当キャップ、ロンドン支局駐在を経て、パリ五輪統括デスク。柔道女子代表の暴力パワハラ問題取材班(代表)として、2013年度新聞協会賞を受賞。共著書に「アスリート盗撮」(共同通信運動部編、ちくま新書)