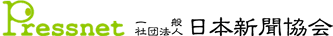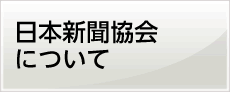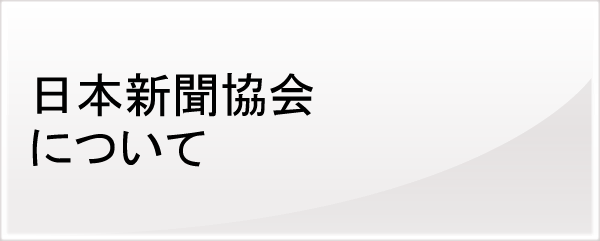- トップページ
- 日本新聞協会について
- 新聞週間・春の新聞週間
- 新聞大会会長あいさつ
新聞大会会長あいさつ
第78回新聞大会 新聞協会長あいさつ
2025年10月15日 東京
一般社団法人日本新聞協会 会長 中村 史郎
第78回新聞大会を東京で開催することとなりました。東京での開催は2010年以来15年ぶり、13回目となります。
今回は東京開催を機に、首都圏の100人以上の大学生の皆さんに参加いただいています。学業でご多忙のところ、足を運んでいただいた学生の皆さん、また協力をいただいた各大学の先生方にお礼を申し上げます。
本大会では、新聞協会賞受賞者と大学生のトークセッションを予定しています。若者の新聞離れが進む中、「ニュースは誰のためにあるのか、何のためにあるのか」について、学生の皆さんと一緒に考えます。新聞大会をより開かれたものにするためにも、有意義なセッションになることを期待しています。
戦後80年の今年、米国でトランプ大統領が再登板し、民主主義や外交・貿易の秩序が大きく揺らいでいます。ガザでの戦争をめぐっては、和平に向けた大きな節目を迎えましたが、なお予断を許さない状況です。ウクライナで続く戦乱は、ロシアの侵攻開始から3年半を超え、いまだに出口が見えません。国内では、参院選での与党敗北を機に政局は混乱し、自公連立政権が解消。いまだにどのような枠組みの政権が誕生するかわからない異例の事態が続いています。急速に浸透する生成AIは社会を根底から変えつつあります。
世の中はめまぐるしく動き、私たち報道機関、マスメディアが担う役割はますます重要になっています。と同時に、わたしたちの真価が問われる事態に直面しています。
昨年来、国政選挙や地方選挙におけるSNSの影響力の高まりが指摘されています。もはや生活インフラの一部となったSNSですが、真偽不明の情報や暴力的な情報が拡散される悪影響も顕在化しています。不正確な情報が選挙結果に強い影響を与えたとすれば、民主主義の根幹を揺るがす深刻な事態です。今年6月、協会は「インターネットと選挙報道をめぐる声明」を発表しました。事実に立脚した報道で民主主義の維持・発展に貢献することが報道機関の責務であることを改めて表明し、参院選ではファクトチェックをはじめ活発な報道が行われた事は一定の成果です。今後も有権者の判断に資する確かな情報を積極的に提供していきます。
同じ6月には「記者等への不当な攻撃に対する声明」も出しました。記者に対する根拠のない誹謗(ひぼう)中傷や侮辱がSNS上で投稿、拡散され、記者個人のプライバシーが侵害される事例も増えています。正当な取材活動が妨げられることで、自由な報道と表現が脅かされてはなりません。協会は今後も記者と取材活動を守り、支援する努力を続けていきます。
生成AIへの対応は、ここ数年で浮上した新しい課題です。生成AIは私たちの業務を革命的に変え、新しい報道の形やサービスを生み出す可能性を秘めています。一方で、多大な労力とコストをかけた報道コンテンツが正当な対価を支払われず、無断で利用される「タダ乗り」は決して許されません。著作権侵害に該当する可能性が高いと考えています。「知る権利」の観点からも、生成AI時代に見合った法制度の整備を急ぐ必要があります。
さらに、こうした厳しい環境にある中で、この一年、協会加盟社において、ジャーナリズムへの信頼、あるいはメディア企業への信頼を毀損(きそん)する事案が起きていることは憂慮すべきであり、極めて残念です。一つ一つの事案について、ここにいる誰もが「他人事ではない」と感じられたはずです。私たちは、SNSとは違う、生成AIにはできない社会的な役割を担っていると自負しています。間違いや失敗をしたときは責任を持って対応することも大切な役割の一つです。そのことを改めて確認したいと思います。
新聞協会は、新聞ジャーナリズムの意義の社会への浸透、事業・組織・財政の見直しを中心とした協会改革を進めています。ジャーナリズムの浸透は、報道界全体のブランド価値を高めることです。報道を支えるメディア企業各社のビジネスは多角化、多様化していますが、業界共通の利益に関わる基盤整備は協会の役割です。その役割を果たすために、協会の体質強化を進めます。会員各社のご理解とご協力をお願いします。
今年6月、協会内に「ジェンダー・多様性に関する協議会」を発足させました。多様な働き方が社会に広がる中、性別や年代、障がいの有無などを問わず、あらゆる人が働きやすい業界になるためにはどうすればよいか。将来に向けた議論を進めています。ここ数年改善が進んではいますが、会場を見渡せばまだまだ圧倒的に男性が多いです。会場にいる若い学生の皆さんに、この姿がどのように映るか。私たちは意識しなければなりません。
まずは私たち自身のリアルな姿を把握するため、協会に加盟する新聞・通信社の全役員・社員を対象とした意識調査を実施します。調査対象が3万人を超える、協会として初めての試みとなります。各社におかれましては、より多くの回答が得られるよう協力をお願いいたします。
最後に、2000年に改訂された新聞倫理綱領は、今日の状況を的確に見通して指摘しています。「おびただしい量の情報が飛びかう社会では、なにが真実か、どれを選ぶべきか、的確で迅速な判断が強く求められている。新聞の責務は、正確で公正な記事と責任ある論評によってこうした要望にこたえ、公共的、文化的使命を果たすことである」。
綱領の原点を改めてかみしめ、新聞人、広くメディアに携わる者としての「矜持(きょうじ)と責任」をもって、私たちの未来を切り開きましょう。ありがとうございました。