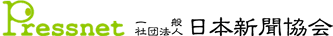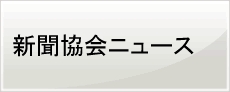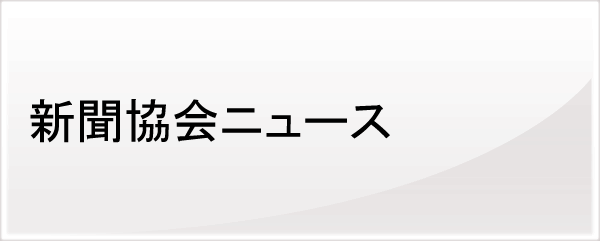<神戸でNIE全国大会>災害記事を防災につなげる 報道・教育関係者ら討議
第30回NIE全国大会初日のパネル討議は、メディアリテラシーの重要性や、選挙・災害時の情報発信、教育への新聞の活用法などについて話し合いました。日本ファクトチェックセンターの古田大輔編集長、兵庫県立大院の阪本真由美教授、西宮市立浜脇中の渋谷仁崇主幹教諭(新聞協会NIEアドバイザー)、神戸新聞社の長沼隆之論説副委員長が登壇。進行は、ジャーナリストで名城大教授の池上彰氏が務めました。
古田氏は、昨年の兵庫県知事選や2025年7月の参院選で、SNS上を中心に偽・誤情報が拡散された問題の背景にはSNSのアルゴリズムの存在があると説明。自分と似た意見ばかりに触れる「フィルターバブル」や、特定の意見が増幅して見え、他の意見が入ってこなくなる「エコーチェンバー」により、情報の真偽を疑うことが難しくなっていると述べました。こうした情報環境下に置かれていることを、NIEの学びの中で子供たちにも知ってもらう必要性があると指摘しました。
県知事選について、長沼氏は公平性を意識するあまり報道に「空白」が生まれ、人々がSNSから情報を得たことが投票結果に影響したと述べました。教訓を踏まえ、神戸新聞社は参院選でファクトチェックを本格化。インターネットに親和性のある世代に響く発信を巡っては工夫の余地があるとしました。
渋谷氏は、子供たちの主権者意識を育むための取り組みに触れました。生徒が「NIEノート」を作成し、記事の切り抜きと、それに対する意見や提案を考える取り組みを紹介。昨年の衆院選の投開票日には、新聞の選挙報道を活用して模擬選挙を実施したといいます。
阪本氏は子供が情報を活用する力の向上が、これからの防災・減災に向けては重要だと説明。過去の災害に関する新聞記事を子供たちに読んでもらうことも、そうした力を育む手段として有効だと説きました。
渋谷氏は、災害を自分自身に関わる問題として捉えてもらい、自発的な行動を促す上でも、NIEが効果的だと説明。東日本大震災に関する記事を授業で扱ったことを契機に、生徒が近隣幼稚園との共同避難訓練を発案し、実行した事例を紹介しました。
(2025年8月5日)