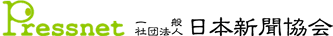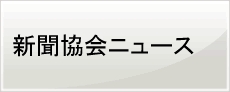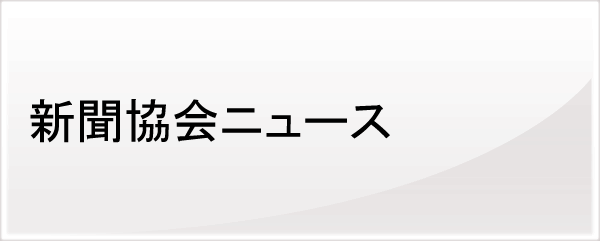<神戸でNIE全国大会・分科会>読み比べでリテラシー育成 記事使い防災意識向上も
7月31、8月1の両日に神戸市で開かれたNIE全国大会2日目の分科会では、兵庫県内の学校教諭による公開授業や実践発表が行われました。東日本大震災について取り上げた地方紙の子供新聞を読み比べたり、記者から話を聞いたりすることで児童が報道の意図を考える公開授業がありました。実践発表では、高校生が新聞記事を使い、小学生向けに地域防災に関する授業を行う事例などが紹介されました。
姫路市立豊富小中学校の前野翔大教諭は、メディアリテラシーの育成を目的に、見出しや写真、レイアウトなどに込められた編集者の意図を児童に考えてもらう公開授業を実施しました。小6の児童24人が東日本大震災の被災地の現状などを報じた岩手日報、茨城、静岡、西日本の子供新聞を読み比べ、地域ごとの伝え方の特徴について話し合いました。
今年3月9日付静岡の子供新聞は、津波の危険性や発生時に取るべき対応に関し、1ページを割いて報じた。地震発生の仕組みを説明した上で、「本州の南側の海底にプレートが押し合う場所があり、30年以内に80%ほどの確率で地震が発生すると言われている」ことを、見出しなども使って強調しました。これに対し、ある児童は「静岡県で大きな被害の恐れがある南海トラフ地震への注意を促すためだと感じる」と意見を述べました。
書かれた時期の異なる二つの大震災関連記事の比較も実施。児童はその違いや背景についても考えました。神戸・上田勇紀記者が2011年と今年3月に書いた記事のそれぞれについて、自身の執筆意図を説明。発生当時は被災状況の周知に注力した一方、今年は被災者が抱えてきた苦悩に焦点を当てたと説明しました。
前野教諭は、情報の向こう側にいる発信者と、その思いに目を向けることが重要だと説明。参加した児童の寿賀颯人さんは、自身が知らなかったニュースの背景や記者の考えに触れ、「深く考えることが面白かった」と振り返りました。
実践発表では、兵庫県立須磨友が丘高の岩本和也教諭が、防災教育における高校と小学校の連携事例を報告しました。同校は23年から生徒がファシリテーター役となり、神戸市立横尾小の児童に対し新聞記事を使って防災について考えてもらう授業を実施しています。
今年2月の授業では、阪神大震災や能登半島地震が発生した直後の避難所の様子などを報じた記事を活用。「避難所で困っていること」を読み取り、その上で自分にできることは何かについて議論しました。小学生からは「避難時は、お年寄りや障害者をサポートしたい」との声が上がったといいます。
岩本教諭は、過去の災害を振り返ることができる点に新聞活用の強みがあると強調。高校生は、教材となる記事を選び、授業の構成を練る過程で、「防災について主体的に考えたり、人に伝えたりする力を育むことができる」と述べました。
(2025年8月26日)