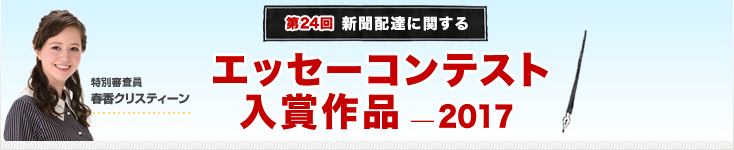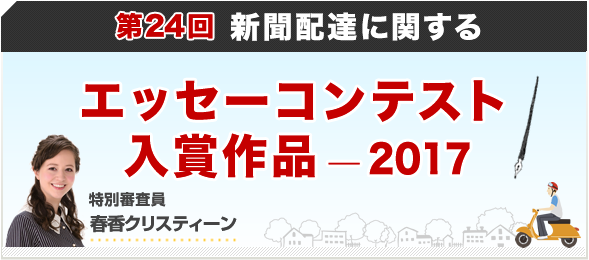最優秀賞
「見ていてくれた人」
青山 未花子(24歳) 新潟市東区

「裏ぶた開いて大音しないよう
『そ―ろ』と投入」(京都新聞社提供)
新聞配達員は、お客様に気が付かれてはいけない。
大学は新聞奨学生として通った。猛暑、大雪、停電、嵐をついて、ポストを目指して走った。心掛けていたのが「新聞配達は意識されないことが最良」ということだった。
毎朝「今日も新聞が届いているな」と考える人はいないと思う。新聞配達員が意識されるのは、不着・雨ぬれ・破け・遅配などで正しく手元に届かなかったとき。だから、意識されるまでもなく当然毎日そこにある、それが新聞のあるべき姿だと思っていた。
けれど、最後の配達日、朝の2時、真っ暗なポストの前で私を待っている人がいた。初めて手渡しで新聞を届けると、引き換えにくれた手紙。
「卒業おめでとう。毎日4年間、新聞を届けてくれたね。あなたの未来は開けている、大きくなれる人。絶対幸せになって。心からありがとう」
見ていてくれた人がいた。うれしかった。
新聞配達員はお客様に気付かれてはいけない。けれど、新聞を介して確かにお客様とつながっていると、強く思う。

「裏ぶた開いて大音しないよう『そ―ろ』と投入」
(京都新聞社提供)
審査員特別賞
「心優しい大うそつき」
村田 友高(41歳) 埼玉県蕨市

「中までしっかり、愛情込めて」
(神奈川新聞社提供)
心優しい友人のA君が、一度だけ、小さな子を本気で泣かせたことがある。
専門学生時代、バイトで夕刊の配達をやっていたA君は、配達先の家でとある幼稚園児の男の子と仲良くなった。
「お兄ちゃん、〝しんぶん〟ってなに?」
「ニュースが書いてあるんだよ」
「ニュース?」
「おっきな出来事。ほら、とっても良いこととか、悪いこととか」
そんな可愛らしい会話を交わした数日後、いつものように新聞を配りに行くと、その子が血相を変えて飛びだしてきた。「お兄ちゃん! ウソつきっ!!」
なぜかA君は大うそつきの悪人になっていた。必死になだめるA君に、しゃくりあげながらその子が答える。「だってボクに弟ができたんだよ!? 書いてなかったよ」
A君は自宅で、自作の号外をその子にだけ配達した。どこまでも、A君は心優しい大うそつきだった。

「中までしっかり、愛情込めて」
(神奈川新聞社提供)
優秀賞
「夜明け前の配達員さん、ありがとう」
河本 久美子(66歳) 神戸市北区

「積み込み」
(西日本新聞社提供)
「Sさんが行方不明です」。まだ肌寒い深夜、私の勤務先である介護施設の夜勤者からの電話。私は施設までの道程で、認知症による徘徊中のSさんを何とか発見できないものかとゆっくり車を走らせたが、寝静まっている住宅地に人の動きはない。
午前4時過ぎにSさんを捜している時、複数の新聞販売所の配達員に出会った。バイクに乗った配達員の方に「白いシャツを着た高齢の男性を見なかったですか?」と声をかけ事情を説明すると、「一緒に捜しましょうか」「見つかればすぐ連絡します」と。その数分後に別の配達員に出会い同様に問いかけると「僕も配達しながら捜します」。その次に出会った配達員は「公園にお年寄りが一人いました」と、情報提供してくれた。別々の販売所の方でしたが、皆嫌がらずに協力してくれ、なんと心強かったことか。うっすらと夜が明けかけた時、「Sさん発見」の連絡があった。
夜明け前から不安な気持ちで、Sさんを捜している時に出会った配達員さんたちの優しい心温まる言葉や対応に、感謝の気持ちでいっぱいになった。本当にお世話になり、ありがとうございました。

「積み込み」
(西日本新聞社提供)
入選(7編)
「鉢植えの水やり」
石井 泰子(72歳) 東京都大田区

「届けるのは新聞と大切な気持ち」
(産経新聞社提供)
田舎出で無類の植物好きだが、東京の自宅には庭が無い。植物を育てるとなると鉢植え以外に手はないのだが、地植えに比べて水やりに数倍気を使わなければならない。泊まりがけで出かける時など、腰水したり日陰に避難させたりと大変な騒ぎになる。
15年ほど前、母が危篤になり取るものも取りあえず帰郷して、そのまま5日も帰れないことがあった。小康状態を取り戻してほっと胸をなで下ろした途端、何の手当もしてこなかった植木のことを思い出した。その時は炎暑続きだったため、全滅していることを覚悟して恐る恐る帰宅した。
ところが鉢植えは全てピンピンしていて出かける時、つぼみだったアサガオは大輪の花を咲かせていた。2階にある玄関に上がると、普段は郵便受けに入っている新聞が、踊り場にビニール袋を敷いて5日分きちんと積んであった。
「ああ、新聞の配達員さんが植木に水やりしてくれた上に、新聞が道路から見えないようにしてくれたんだ」とすぐに分かった。新聞と優しさの同時配達に心がほっこりした。

「届けるのは新聞と大切な気持ち」
(産経新聞社提供)
「頼れる先輩」
片田 薫(37歳) さいたま市南区

「夕刊到着。さあ、読者の元へ」
(東奥日報社提供)
「女の子ぶっちゃって」
カゴいっぱいに積み上げた新聞の重みでバランスがとれず、自転車を倒してしまった私に、指導役の先輩は苦笑い。女の子ぶっている気はサラサラないが、配達序盤から不安な気持ちになったのは確か。
大学生活も、一人暮らしも、新聞配達も、初めてづくしの18歳。
新聞の折り畳み方やカゴへの積み方、順路記号の読み方から、配達終わりにほっと一息つける自販機の場所まで、親切に教えてくれた3歳上の先輩。
原付きバイクに乗り始めるときには、どんくさい私のために、自転車で伴走しながらギアの切り替えを教えてくれた。
雪の日、自分も早く配達に出たいだろうに、戸惑う私の分まで、原付きのタイヤにチェーンを巻いてくれた。
「あきちゃん、パパ起こして新聞とってきて」
あれから17年。
頼れる先輩は父となり、どんくさい後輩の尻に敷かれている。

「夕刊到着。さあ、読者の元へ」
(東奥日報社提供)
「父の音」
神野 榮美(61歳) 大阪府松原市

「僕もお手伝いできるよ」
(日本経済新聞社提供)
歩きはじめた孫が、初めて私の部屋に新聞を持ってきてくれた。小さな手から新聞を受け取った瞬間、ある記憶がよみがえった。
幼い頃、父に新聞を届けるのは私の役目だった。父は苦学生だった頃、新聞配達の経験がある。その時のしぐさを時々やってみせてくれた。入れやすくするため、二つ折りにされている新聞をもう一回折り、スウーとしごいて、独特の音を出してから新聞受けに入れたそうだ。それは楽器のギロにも似た不思議な生き物のような音で小気味良く響いた。私は何度まねてもできない事を、手の大きさのせいにした。
朝まだきの冷気の中、何百軒とある配達の句読点を打つように、父はけじめの音を町中に響かせていたのだろう。
父は新聞を4紙とっていた。物知りで聞けば何でも答えてくれた。特に政治のことは詳しく、話し出すと止まらなくなり疎ましくなることもあったが、今はその声が欲しい。自分が聞かれる立場になって、父の知識の源泉は新聞配達だったと実感している。
4紙とまではいかないが、もう1紙増やそうかと思っている。

「僕もお手伝いできるよ」
(日本経済新聞社提供)
「20年以上、気になっていること」
久保 光余(63歳) 兵庫県川西市

「お店の配達員は……左利き!」
(京都新聞社提供)
20年以上前、郊外から通勤していた私の朝は早く、よく似た環境の新聞配達の少年に親近感を抱いていた。ある朝私は、少年をねぎらうつもりで新聞を手渡しで受け取ろうと考え、夜明け前の薄暗い玄関先で待っていた。
どんな日にも必ず新聞を届けてくれる少年に感謝の言葉が伝わるだけで、私は満足していたが、主人からは、毎朝、暗闇でおばさんにじっと待たれているのはかなり怖いはずだと真顔で言われてしまい、そんなことはないと反論しつつも私は、翌朝から新聞の直接受け取りをやめてしまった。
すると数日後、新聞販売店の社長に、配達の子が奥さんを突然お見かけしなくなったと言って体調を心配していたと聞かされ、私はうれしくなって主人に報告した。主人も新聞少年の優しさに感動していた。
あの時の新聞少年も、今や30代の立派な社会人なのだと思うと感慨深い。そして私は、あの時本当に少年を怖がらせていなかったのだろうかと、今でも気になっている。

「お店の配達員は……左利き!」
(京都新聞社提供)
「午後4時のヒーロー」
渋谷 真希(58歳) 札幌市白石区

「チラシのセットも、ひとつひとつ丁寧に」
(佐賀新聞社提供)
一人息子が小学生になると、夕方の心配事が増えた。職場にいる私は、無事に帰宅しただろうかと不安になる。
肌寒い5月のある日、風邪で早退した私は、玄関前でランドセルにもたれて座り込んでいる息子に出くわしはっとなった。
鍵は持たせてあるのにどうして。
「俺ね、一人で家に入るの怖くて嫌なんだ。いつも新聞のおじさんが来るの待ってるの」
入学したての頃、うまく鍵を開けられず玄関前でもたもたしていると、夕刊配達のおじさんが声をかけて手助けしてくれたという。
ああそうだったのか。息子は毎日ほぼ定時にやって来るおじさんを、すっかり頼りにしていたんだ。思いがけない善意に守られていたことに気づいて、胸が熱くなった。
「いつもマスクして自転車に乗ってるの。でも遅くなってバイクで来た時もあるんだよ」
届けられたのは新聞ばかりではなかった。

「チラシのセットも、ひとつひとつ丁寧に」
(佐賀新聞社提供)
「おいしい新聞」
外山 乃梨子(32歳) さいたま市見沼区

「配達準備中」
(信濃毎日新聞社提供)
「お父さん、新聞読むのやめなよ。ごはん冷めちゃうよ」「ん……」
「ほら、新聞は後でいいでしょ、冷めないんだから」「いや……冷める」
「え?」「この新聞は、まだあったかい。さっき届いたばかりのやつだ。前川のじいさんが、いつも一番に届けてくれるんだ」
「お父さん、お仕事行くのが早いからね。でも、新聞があったかいわけないでしょ」「いや、あったかいぞ。お父さんの仕事には、アツアツの情報が必要なんだ。新聞ってのは、出来立てアツアツの情報の塊だ。それを冷めないうちに、前川のじいさんが届けてくれる。雨の日も風の日も、俺の出社前に届けてくれる。その気持ちがな、何よりもあったかい。冷めないうちに読みたいんだよ」
「いいなあ、前川のおじちゃん、冷めないうちに読んでもらえて。私のごはんは……」「すまんすまん。いただきます」
「ねえお父さん、私にも新聞読ませて。あったかい新聞、何だかとってもおいしそう」
私が朝刊を読む、きっかけとなった思い出です。

「配達準備中」
(信濃毎日新聞社提供)
「万年筆」
西村 英紀(35歳) 福岡県宮若市

「店内業務」
(東京新聞提供)
中学、高校と新聞配達をしていた。その中でもまず最初に配達しなくてはいけない家。雨であろうが、雪であろうが、なんと台風であろうが玄関先でいつも新聞を待っているおじいさんがいた。
はじめはおっかなビックリで会話もなかったが、5時までに届いてないとのおしかりの電話があったりで、少しずつコミュニケーションをとるようになり、日常会話をするようになった。たまに、早朝にもかかわらず、おやつやジュース等もいただいて色々お世話になった。
私が大学受験のため今月いっぱいで辞めますと伝えると、最後の日に入学前祝いにとモンブランの万年筆をいただいた(その時価値を全く知らなかった)。
卒業して実家に帰った際、お礼に伺ったが、家がなくなっていた。前にあるお店の方に尋ねると、数年前に亡くなり、去年取り壊したそうだ。今でも合格した時にあいさつにいけばよかったと後悔している。
社会人になり、仕事着の胸に今でもいただいた万年筆が輝いている。あの時はありがとうございました。感謝しています。

「店内業務」
(東京新聞提供)
最優秀賞
「心のエネルギー」
栁谷 杏那(13歳) 青森県八戸市

「伝統の街並みを配達」
(北日本新聞社)
「婆は、あなたのママが小さいころ背中に背負い新聞配達をしていたのよ。免許がなかったから、雨、風、雪の日も自転車の荷台に新聞を載せ、高台まで押しながら上り、団地周辺や家の近くを約二百件。小さな子供がいると仕事に就くことが難しく生活の足しにと始めたのよ。でも、子を背負い配達する婆の姿に配達が遅れてもぐちも言わず玄関先で待っていてくれたり、子供さんにとお菓子を握らせてくれたり、さらには新聞販売所の方が終わってから手伝いに来てくれたり、たくさんの人の情けに助けられ感謝したよ。さりげない言葉や行動に涙があふれたよ」
ポストに入る新聞の音を聞くたび祖母の話を思い出します。
毎日手にする新聞ですが、自分が手にするまでにも目に見えない風景があります。新聞から伝えられるさまざまな出来事に興味がわきます。楽しい記事ばかりではありませんが、世の中に起きているどんなことでも私が成長していくための心のエネルギーです。

「伝統の街並みを配達」
(北日本新聞社)
審査員特別賞
「父のあたたかみ」
中山 晶(17歳) 石川県津幡町

「大事な新聞を丁寧に手渡し」
(朝日新聞社提供)
深夜2時頃から父が配達さんに「お願いします、行ってらっしゃい」と言う声が作業場から聞こえる。私の家は新聞販売所を営んでいる。子供の頃の私は家業である新聞配達の仕事が大嫌いだった。
新聞配達に休みはほとんどなく、休刊日があっても当時小学生だった私の休日と重ならず、遠出の旅行に連れて行ってもらった記憶がない。父が普通に休みがある会社員だったら良かったのにと思っていたが、高校生になった今は父の仕事を誇りに思えるようになった。
父は仕事上、地域の人との関わりが深いため、誰にでもあいさつをする習慣がついている。車の運転中でも道を歩いている人に会釈をする。そして父はいつも笑顔で人と話す。もし、私が小学生の頃願っていたように父が普通の会社員だったら、父は親しくない人にまであいさつをしていないかもしれない。
高校生になってようやく、毎日休みなく仕事を続ける父のすごさ、そしてあたたかみを知ることができた。
今は家業を誇りに思う。

「大事な新聞を丁寧に手渡し」
(朝日新聞社提供)
優秀賞
「僕は書いて、彼は届ける」
遠田 剛志(14歳) 東京都新宿区

「朝焼けと共に疾走と」
(神奈川新聞社提供)
「ブルルル」。毎日、早朝に忙しく走る新聞配達のバイク。
今日は少し音が違うな、と思い眠い目をこすりながら窓からのぞいた。
いつも新聞を配達してくれているおじさんの後ろに、一人の青年がいて一生懸命にメモをとっている。メモをとり終えるとバイクにまたがり、おじさんの後を追いかけて行った。
きっと引き継ぎかな。その日の午後、夕刊配達には早すぎる時間に、彼はもう一度現れた。今度は一人で、空っぽのバイクで。よく見ると、朝のメモを見ながら、配達先の復習をしている様子だ。すごい。
僕はこの春から、新聞社のジュニア記者として活動をしている。彼と同じ、新聞にかかわる「一年生」だ。その分新聞を作る苦労も少しは分かっているつもりだ。
読者へ新聞を届けるリレー。そのアンカーとして、彼は毎日休まずバイクにまたがる。積まれた新しい新聞。その価値を少しでも高められるよう、僕も彼に負けずに頑張ろう。

「朝焼けと共に疾走と」
(神奈川新聞社提供)
入選(7編)
「希望を与える職」
柏崎 友祐(16歳) 青森県おいらせ町

「明るい希望へ」
(福島民報社提供)
新聞配達といえば、あまり目立つことのない仕事だと思う人が多いかもしれません。確かに表に出る機会は少ないかもしれませんが、僕は非常に夢のある仕事だと思います。
僕がそのように思い始めたのは、6年前の東日本大震災からでした。当時9歳だった僕は、突然の強い揺れや、今までにないほど長い停電で頭が真っ白になり、恐怖に飲み込まれそうになりました。心の支えや情報源となるテレビも停電の影響で見られなくなり、絶望寸前でした。
しかし、翌朝郵便受けを見に行くと、いつも通り配達員の人が新聞配達をしていました。自分も被災しているはずなのに、その配達員の人は普段と同じように働いていて、思わず心を打たれました。自分も配達員のように震災に負けないようにがんばろうと思いました。
この日以来、僕は新聞配達という仕事は希望も渡してくれる良い仕事だと思いました。僕も将来、希望を与えられるような職に就きたいです。

「明るい希望へ」
(福島民報社提供)
「配達の人に感謝」
坂爪 莉子(17歳) 横浜市磯子区

「海の街の配達」
(毎日新聞社提供)
新聞配達の人は、毎朝私に世界を見せてくれる。
「今の時代、珍しいな」
前のスーツ2人組が、電車内で朝刊を広げる私の姿に目を見張っていた。一方で彼らのスマホにはネットニュースが表示されている。
「莉子ちゃん、新聞? やばいね!」
友達が私に声を掛ける。始業の1時間前には教室に着き、切り抜きをするのが私の日課だ。新聞は新たな発見であふれているが、まだそれに気づいていない同級生も多い。
スマホの普及とそれに伴う情報の氾濫。また、日本人の急激な国語力の低下。「やばいね」こそ本当にやばいのだ。新聞は信ぴょう性が保証され、全ての記事に目を通すことができ、さらに確かな国語力を養ってくれる。配達の習慣、この日本の朝の風物詩こそ、我々の必要な情報のみをえりすぐっていると言えるだろう。デジタル時代に生きる我々の世代は、新聞配達で届く情報の信頼性が高いことを頭に入れるべきだ。
毎朝早起きをしてくれている新聞配達の人に感謝しながら、今日も私はポストから新聞を取り出す。

「海の街の配達」
(毎日新聞社提供)
「祖母からのプレゼント」
鮫島 舞雪(15歳) 鹿児島県南さつま市

「迅速、丁寧に」
(信濃毎日新聞社提供)
私には毎朝届くプレゼントがあります。それは祖母が頼んでくれた新聞です。高校3年間届くプレゼントです。
なぜ私にとってプレゼントなのか。
それは私たち姉弟の成長を願って頼んでくれたものだからだと思っています。新聞を頼むときに祖母から「新聞を読むことで今の社会だったり世界のことをしっかり学ぶのよ。がんばってね。おばあちゃんは応援してるからね」と話してくれました。
新聞というプレゼント。大きな愛を感じるプレゼント。
これからの3年間は私にとってすごく大事な3年間です。その3年間さまざまなことを考え、感じ、成長できる瞬間に、新聞で気付き、考え、学ぶことができます。
大きな成長ができる時期に「新聞」というプレゼントをくれた祖母に感謝しきれません。夢を大きく持って頑張りたいです。

「迅速、丁寧に」
(信濃毎日新聞社提供)
「ヒーロー」
嶋 あずみ(13歳) 東京都板橋区

「安全運転で読者の元へ」
(東奥日報社提供)
部活帰り、いつもの道を一人で歩いていた。すると、家の近くの道路で人だかりができていた。近寄ってみると、おじいさんが倒れていた。どうやらふらついて倒れ、動けなくなってしまったらしい。そんな大変な時、おじいさんの一番近くで頭を支えている人がいた。毎日見かける配達員さんだ!
その方の自転車カゴには、まだたくさんの新聞が残っている。しかし、それを気にする様子もなく何度も「大丈夫ですか」と声をかけ続けていた。私も心配でずっと見ていたが、おじいさんは見事回復した。本当に良かった。
私は昔から、人の目を気にしてしまい自分からは何もできない性格だ。だから、勇敢な行動をとった配達員さんが少しうらやましかった。おじいさんの無事を見届けた後、「さてと」と自転車で走り出す配達員さん。その後ろ姿は夕日に照らされ輝いていて、まるでヒーローのようだった。
その日から、私は「次は自分から誰かを助けよう」と思うようになった。

「安全運転で読者の元へ」
(東奥日報社提供)
「一日の境界線」
下浦 晴香(18歳) 京都市左京区

「配達準備」
(東京新聞提供)
カタン―。今日もペンを動かしていると、家の郵便受けが音を立てるのが聞こえてくる。新聞配達員の方が新聞を届けに来たのだ。
夜はできるだけ早く寝て、まだ外が暗いうちに起きた後は、明るくなるまで勉強する。それが、中学生の頃からの私の生活スタイルだ。この時間、家族や連絡を取り合う友達はもちろん誰も起きていない。
窓の外に広がる街もひっそりと静まり返っている。勉強や読書に没頭するにはちょうど良い。朝まで寝ている時と違うのは、起きた後の自分が、昨日の延長線上にいるような感覚を覚えることだ。楽しかったことの余韻に浸る時もあれば、辛かったことを思い返す時もある。そうこうしているうちに、新聞が届くいつもの音が聞こえる。
家族と交わすあいさつよりも先に朝が来たことを知らせるこの音は、私にとって、曖昧な昨日と今日の間に境界線を引いてくれる存在だ。
配達員の方への感謝と共に、今日にふさわしい真っさらな気持ちを生む、そんな音が好きだ。

「配達準備」
(東京新聞提供)
「嫌いから好きへ、尊敬に」
中村 美鈴(13歳) 神奈川県逗子市

「夏の昼間のチラシ作業」
(佐賀新聞社提供)
「ニュースは毎日、チェックするの」
私の将来の夢は社会科の教師。それを知っている社会科担当の先生に、毎日言われてきた。
私の父は新聞配達員。でも父とは口を利かず、新聞にも興味を持たなかった。
ある時、父に声をかけられた。
「一度で良い、新聞読んで。一生のお願い」
休みの時間のたびに読んだ。一文字一文字に力がこもっていた。作成者すべての気持ちが。
ある夜、「ありがとう」と言った時、涙が出た。それ以降私は毎日、新聞を読んでいる。
新聞配達員でないと、あの一言の説得力はなかった。新聞を読んでから、「物知り」と言われるようになり、これも父のおかげ。また一つ、誇れる仕事「新聞配達員」を見つけた。
嫌いから好きへ、尊敬へ。配達員として、頑張っている父を心の底から応援している。配達員に感謝、私は今日も新聞を読んでいた。

「夏の昼間のチラシ作業」
(佐賀新聞社提供)
「誰かのために」
我妻 あみ(17歳) 宮城県美里町

「配達後に食べてね」
(毎日新聞社提供)
隣町に住む私の祖父は、新聞配達を始めて12年になる。
まだ暗いうちに起きて犬の散歩をし、大きな新聞の束を持ってバイクを走らせる。雨の日も雪の日も、これが祖父の日課だ。
ある朝、我が家に一本の電話が掛かってきた。祖父が凍結した路面に滑り、バイクごと転倒してけがをしたのだ。
私はすぐさま病院に向かい、不安を抱えて会いにいった。病室で苦しそうにしながら言った祖父の一言を、私は今でも忘れることができない。
「じいちゃんはな、新聞配達が好きなんだ。新聞を届けると笑顔が返ってくる。地域の人たちの安心した顔を見たり、ねぎらいの言葉を掛けてもらった時は、心がほんのり温かくなるんだよ」。だから早く復帰しないとなあ、と屈託なく笑う祖父の瞳は、きらきらと輝いていた。
それから数年がたった。祖父は今日も元気はつらつと、配達に出かける。
「気をつけてね。みんなが待ってるから」
そのたくましい背中に向かって、私はそっとつぶやいた。

「配達後に食べてね」
(毎日新聞社提供)
最優秀賞
「日本一の新聞屋さん」
糸原 愛理(12歳) 広島県庄原市

「出発」
(西日本新聞社提供)
日本一の新聞屋さんが、私の住む町にいる。
2017年2月10日、私が住んでいる、広島県庄原市高野町で、全国最多の24時間降雪量71cmを記録した。前日までに降った雪と合わせて、125cmになった。
その日の朝、お父さんは新聞を読んでいなかった。新聞が届いていなかったからだ。
小学校は1、2時間目が休みになり、大雪で、駐車場から車が動かせなくて、お父さんも仕事を休んだ。
外で雪かきをしていたお父さんが、新聞を持って家に入ってきた。新聞屋の宮野さんが歩いて届けてくれたらしい。車を止める場所もないくらい大雪だから、すごく遠くから歩いてきてくれたんだと思う。まだ雪がたくさん降っていたけど、新聞はぬれていなかった。大事に持って来てくれたんだなと思った。
いつも新聞が届くのは当たり前だと思っていたけど、こんな大雪の日でも、町のみんなに、大切に届けてくれていることを知った。
日本一たくさん雪が降った日に、新聞を届けてくれた宮野さんは、日本一の新聞屋さんだと思う。

「出発」
(西日本新聞社提供)
審査員特別賞
「みちの音」
清水 煌生(8歳) 福井県坂井市

「山小屋行きの新聞」
(北日本新聞社)
ぼくは、夜中に目がさめた。きょうは、すごいあらしだ。風がビュービューと家をおす。
ぼくは、母をおこした。すごいかみなりの音にしんぞうがとび出そうだった。弟は、まったくおきない。さすがだ。
「どうしたの? こわいの?」と、聞かれた。父がいないせいか、いちだんとこわくかんじた。「うるさくてねむれない」と、言ったとき、雨がいちだんとうるさくなった。そんな中、はじめて聞く音がした。
「ゴト、ガタン」「なんの音?」と、母にたずねると、しんぶんが来た音だと、教えてくれた。ぼくは思わず、「こんな時間におしごとしているの? それにこの天気だよ」。「そうね、大へんでしょうね。でも、こんな日にわたしたちいがいにおきている人がいると、ちょっとあんしんしない?」。ぼくはわかった。母もこわかったんだ。
いつも6時までねているぼくは、しんぶんがいつ来ているのか知りませんでした。きっと毎日しんぶんをまっている人がたくさんいると思います。
しんぶんやさんは、しんぶんをとどけてくれるだけじゃなく、ちいきのあんしんもとどけてくれているのだと思います。
さいごに、ぼくの家にしんぶんをとどけてくれてありがとうございます。

「山小屋行きの新聞」
(北日本新聞社)
優秀賞
「いつもありがとう」
富永 梨緒(11歳) 千葉県八千代市

「良い仕事は、良いリズム。培ってきたプロの仕事」(産経新聞社提供)
「カタン」と新聞が届く音。母は毎朝この音で目を覚まし、すぐに小説を読む。父は朝食の時、1面からじっくり読む。私は天気予報を見る。私たち家族の1日は新聞で始まる。
毎日配達してくれているのは西口さんだ。私を見かけると「また背が伸びたね」「今年のミカンは昨年よりずいぶん多いね」「かぼちゃが大きくなってるね」などと声をかけてくれる。いつも笑顔の優しいおじさんだ。
西口さんは色んな所に出没する。お昼に新聞の大きな束を抱えて団地の階段をのぼっていたり、私が住んでいる所から遠く離れた所で配達をしていたりしていると思ったら、夕方にはうちに来る。
西口さんはどんな時にも配達に来てくれる。台風で学校が休みの日も、寒くて私が起きられない朝も、新聞を届けてくれる。当たり前のように新聞はうちに来るけれど、それは大変な時にも、西口さんがまじめにきちんと届けてくれるからだ。
いつもありがとうございます。これからも元気でいてくださいね。

「良い仕事は、良いリズム。培ってきたプロの仕事」(産経新聞社提供)
入選(7編)
「大切なこと」
石野 美宙(12歳) 東京都練馬区

「サービス向上を目指して研修中」
(読売新聞社提供)
夏休みになったと同時に始まった、マンションのエレベーター工事。2週間もエレベーターが止まる過酷な試練が、上の階の住人の関係者らを巻き込むことになった。
新聞を購読していたのは、マンション内で唯一うちだけで、しかも最上階だ。毎朝毎夕、いつもおじいさんがうちだけのために持って来てドアポストに入れてくれていた。
母は「ロビーポストに入れて下さい」と、工事が始まる前に連絡をしていた。真夏のマンションの階段を、おじいさんが上って来るのは気の毒だからだ。
ところが、おじいさんは「何てことないから」と言って、2週間も1日2回、階段を上って届けてくれた。
「申し訳ないわ」と母が言うと、おじいさんは「いつもありがとう」と、逆にお礼を言って、にっこり笑って手を振った。私は、おじいさんの「ありがとう」の言葉が心に染みた。大切なことを、おじいさんから学んだ気がした。

「サービス向上を目指して研修中」
(読売新聞社提供)
「ぼくのしんぶん」
金田 未來(7歳) 仙台市青葉区

「どこへでも」
(福島民報社提供)
「うちのしんぶんは、ちばからこうそくどうろをつかって、とどけられているんだよね」。ぼくがそういったとき、お父さんもお母さんもわらいました。
ぼくは、1年生になるときに、仙台にひっこしをしました。ひっこしをしても、あさはしんぶんがとどき、まいしゅう木よう日には、ぼくのしんぶんもとどきました。
ぼくのしんぶんは、ピン!としていて、何だかいばっているみたいです。「ちばからきたんだぞ!!」といっているみたいです。
でもぼくは、しんぶんはいたつの人に、まだあったことがありません。まい日、とおくから休まずにとどけてくれて、すごいなあとおもいます。
いつかもっと早おきして、「ありがとう」とつたえたいです。それがつたえられない今は、ぼくのために大じにとどけてくれたしんぶんを、すみずみまで大じによみます。そうすることが、「ありがとう」のかわりになると、ぼくはしんじています。

「どこへでも」
(福島民報社提供)
「地域の見回り」
島田 怜央(12歳) 長野県下諏訪町

「素早く正確に」
(西日本新聞社提供)
ぼくの母は新聞販売店で働いている。ぼくもたまに事務所について行くときがある。そうすると新聞配達をしているおじさんたちがいつも、「一緒に新聞配るか?」と笑ってぼくをからかう。ぼくは「絶対やだよー、早起きいやだし」といつも言う。
ある日、そこの所長さんが警察から感謝状をもらう出来事があった。冬の新聞配達中の早朝まだ真っ暗な中、おじいさんが道でうずくまっていたのを見つけて助けたからだ。おじいさんは認知症で、帰る家が分からなくなって寒さで凍えて動けなくなっていたそうだ。
感謝状をもらった所長さんは「毎朝必ず新聞を配達することは地域の見回りをしているようなもの。犯罪や事故を防ぐ手助けもできたらうれしい。お客さんと顔を合わせることは少ないが、新聞を配ることでつながっていると思っている」と言った。
なんかカッコいいと思った。ぼくも大きくなったら新聞配達をしてみてもいいかな、とちょっとだけ思った。

「素早く正確に」
(西日本新聞社提供)
「なんどたおれても」
図司 実早紀(8歳) 愛知県小牧市

「利尻島での配達」
(北海道新聞社提供)
わたしのお父さんは、中学2年生の時、しんぶんはいたつのしごとをしていました。
毎朝お父さんは早くおきて、しんぶんをじてんしゃにつみました。おもくてフラフラして、何回もじてんしゃごとたおれて、しんぶんが道にちらばったそうです。雨の日もバシャーとしんぶんがちらばってぬれて、おこられたと話してくれました。雪の日もころんだり、犬にほえられたり、くらいだん地ではおばけが出そうだったりと、こわい思いもしたそうです。お父さんはつらい時もがんばってよかったと教えてくれました。
わたしはさか上がりができません。れんしゅうしてもしっぱいばかりでつらいです。でもお父さんが何回もたおれながらしんぶんをとどけたように、わたしも何回もれんしゅうしたら、きっとできると分かりました。
こんどはお父さんにわたしのがんばるところを見てよろこんでもらえたらうれしいです。

「利尻島での配達」
(北海道新聞社提供)
「手元に届いてこそ」
福田 映月(11歳) 奈良県生駒市

「雨濡れ対策もしっかりと」
(信濃毎日新聞社提供)
「ただいま」
「おかえり。いってきます」
これが、お父さんと私の朝のあいさつです。私の家は新聞販売店をしています。お父さんが仕事を終えて家に帰ってくるころ、入れかわりで私が学校に向かって出発します。
お父さんは、教えてくれました。新聞が各家庭に届くまでには、たくさんの人の力が必要で、まず新聞の記事を書く記者さん、新聞を印刷する印刷会社の人たち、新聞を運ぶ運送会社の人たち。そして、一軒一軒、大切に届けてくれる配達員の人たち。
どんなにすばらしい新聞でも、読んでくれる人の手元に届かなければ意味がありません。当たり前のように家にある新聞も、これだけたくさんの人に支えられていることを知りました。
毎日毎日休むことなく新聞が届くのを待ってくれている人たちのために、がんばっているお父さん、支えてくれているすべての人に、ありがとうを伝えたいです。

「雨濡れ対策もしっかりと」
(信濃毎日新聞社提供)
「笑顔を届ける人」
逸見 優翔(11歳) 鳥取市吉方町

「総本山善通寺。おもてなしの心とともに」
(四国新聞社提供)
私が3、4さいの頃、新聞を届けてくださっていたおじいさんのことだ。集金に来る時、よく犬を連れて来ていた。聞いてみると、「おじいさんのことが大好きで『ついていく』というから連れて来るんだ。近所の犬だけどね」と笑顔で教えてくれた。楽しいおじいさんだ。
「大きくなったね」と必ず声をかけてくださり、話をするのが大好きで、母によると1、2時間くらいいろいろなお話をしていたらしい。まだ小さかった私はお話よりも犬と遊べる方が楽しかったが、おじいさんは楽しそうなイベントを見つけては紹介してくださったり、鳥取の歴史のことだったり……。今の私が聞きたいような話だったようだ。本当の孫のようにかわいがっていただいた。
今、おじいさんは天国にいる。天国でもきっとたくさんの笑顔を作っていると思う。
私は、笑顔はいろんな人を幸せにできると思う。私も笑顔を届けられる人になれるようにがんばろうと改めて思った。

「総本山善通寺。おもてなしの心とともに」
(四国新聞社提供)
「じぃじおはよう。おかえりなさい」
山根 一輝(10歳) 仙台市太白区

「函館市恵山のふもとでの配達」
(北海道新聞社提供)
祖父は15年間新聞配達を続けている。ある冬の日に足のケガをした。ぼくは、身体が心配で「仕事辞めなよ」と言うと、「でもな、朝日を見ながらきれいな空気を吸って配達すると健康になるんだ」と笑顔で話してくれた。
1か月後にケガから復帰すると、お客様から「あなたのバイクは必ず4時に聞こえるけど、しばらく遅かったね。身体こわした?」と言われたそうだ。お客様にとって祖父のバイク音は朝を告げる時計の役目も果たしていた。
新聞配達は地味な仕事だと思っていた。でもお客様からの「おはよう」や「ありがとう」と笑顔で言われている祖父の姿を見ていると、必要とされている大事な仕事だと思う。
新聞は取材、編集、印刷、運送と多くの人の手と思いがこもっている。
祖父はアンカーとして新聞というバトンをお客様に届け続けている。それはとてもすごいことだ。
仕事をしている祖父はとても輝いている。

「函館市恵山のふもとでの配達」
(北海道新聞社提供)
(敬称略)