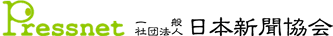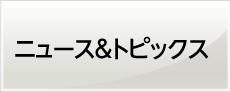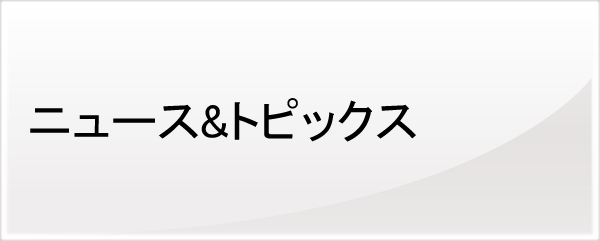- トップページ
- 新聞協会報・地域を伝える(旧・記者駆ける)
- 地震対策 指針と実態乖離
2025年 5月13日
地震対策 指針と実態乖離
高知 「避難所は変わるか」 4月10~12日(全3回)
昨年8月、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表された。発災時、高知県では約21万7000人の避難者が生じると見込まれる。報道部の山崎彩加記者は「いつ起きてもおかしくない」と危機感を強めた。連載では地元の避難所の現状と課題を掘り下げた。
連載は冒頭で、1970年の高知市内の避難所の写真を紹介した。仕切りなく大勢が雑魚寝する光景は、現在まで「変わっていない」と強調する。
能登半島地震の被災地で見た光景も取り上げた。石川県珠洲市では自治体指定の避難所から被災者があふれた。自主開設された避難所は1人1畳にも満たない広さで、トイレもままならなかったという。南海トラフ地震の被害想定では、高知市で4万人分の避難所が不足する。山崎記者は「高知でも同じ状況が起こり得ることを伝えたかった」と話す。
自治体からも課題を聞き取った。避難所に指定される公立学校体育館の9割超に空調設備がない現状を紹介。「エアコンなしで我慢させる避難所は無理」とする専門家の見解を併せて伝えている。
国は昨年末、避難所運営に関する自治体向け指針を改定した。国際基準にのっとり、「1人当たり約2畳以上のスペースの確保」「20人当たり一つ以上のトイレの設置」などを掲げる。新指針を当てはめると県全体で6万人分の避難所が不足するという。自治体担当者は国の理念に共感する一方、人的・財政的にリソースが足りないと苦悩の声を漏らす。山崎記者は「指針と現場の乖離に焦点を当て、行政に問題提起する狙いもあった」と話す。
山崎記者は「連載をきっかけに、防災を人権問題として捉える意識が強くなった」と語る。今後は、高齢者や障がい者から見た避難所の在り方など、バリアフリーの観点から取材を続ける予定だ。(丈)
※連載はこちら(他社サイトに移動します)