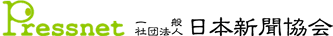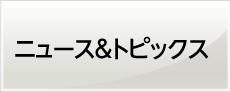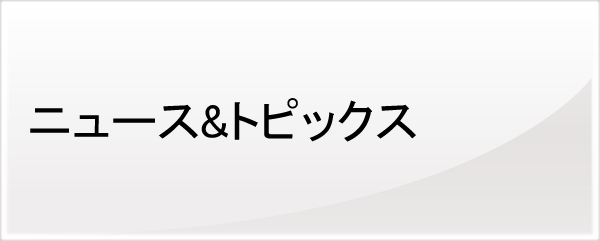- トップページ
- 新聞協会報・紙面モニターから
- 国際法守らぬ「暴挙」批判 米国がイラン爆撃
2025年 7月22日
国際法守らぬ「暴挙」批判 米国がイラン爆撃
外交的解決の重要性指摘
米軍はイラン時間6月22日午前2時半(日本時間午前8時)ごろ、イラン中部フォルドゥを含む複数の核施設を軍事攻撃した。米国によるイラン本土爆撃は初めてとされ、地下80㍍にあるウラン濃縮施設の破壊に特殊貫通弾(バンカーバスター)が使用された。今回の軍事行動を巡り、各紙の社説では、外交による解決や法の支配の重要性を強調するとともに、トランプ氏の国内外の意見を無視した独善的な姿勢に批判が相次いだ。
同盟国軽視も甚だしい
まず、今回の攻撃が国連憲章や国際法に反するという点で多くの社説が共通している。朝日は「侵略戦争を続けるロシアに続き、同じく安保理常任理事国である米国までもが国際法を犯した」と指摘。日経も「主権国家への武力行使は、法の支配という規範を損ねる暴挙といわれても仕方がない」と断じ、西日本も「今回の攻撃は国連憲章に違反する」と述べた。
さらに、米国の行動が一方的かつ拙速であったという批判も多い。読売は「外交で実績が乏しい中、トランプ氏は成果を急いでイラン攻撃を決断したのではないか」と分析し、中国は「民主的な手続きを軽んじた。独裁国家のように重要な軍事行動を決め、実行に移したことに背筋が寒くなる」と書く。岩手日報は「イランから邦人退避を進めているさなかでの攻撃は、同盟国軽視も甚だしい」と非難した。茨城、下野、山梨日日、岐阜などは「宣戦布告無き一方的な軍事行動は、不意打ちに等しい」とし、日本海、山陰中央、佐賀、大分合同などは「米国の外交的信用と名誉は地に落ちた」と嘆いた。北國は「米国、ロシア、中国といった軍事大国は必要とあらば、国際法を無視して行動する。国際法には罰則や強制力がなく、法を守らせる手段もない。私たちは、そんな『弱肉強食』の冷酷で、非情な世界に生きているという事実をあらためて直視すべきだろう」と国際法の限界と現実の非情さを説いた。
イランがウラン濃縮製造を加速させ、イスラエルや米国との対立が深刻化した背景には、第1次トランプ政権による核合意離脱があるとの視点も多い。新潟はイランとの「核合意から、2018年になって一方的に離脱したのは、第1次トランプ政権だ」と明言し、静岡は「そもそもイランを核開発に追い込んだのは、第1次トランプ政権」と強調。山陽も同様に「戦火の種をまいたのはトランプ氏だ」と断定した。愛媛は「トランプ氏は自らの短絡的な行動が世界の不安定化を招いていると自覚すべきだ」とただすなど、イランを核開発に追い込んだ責任の一端は米国にもあるとする認識で一致する。
外交努力の欠如も論点だ。毎日は「力による解決は禍根を残し、惨禍が繰り返されることになる。外交的な解決でなければ、根本的な問題を取り除くことはできない」と結び、高知も「緊張緩和へ外交交渉に立ち返る必要がある」と呼び掛ける。秋田魁は「日本を含む各国は、米国とイランが協議の場で政治解決を目指すよう外交努力を尽くすべきだ」と注文し、南日本は、同盟国として日本には「国際法を守ることが対中政策でも重要だということを米国に説く役割もあるはずだ」と総括した。
米国の軍事行動が他国に対して危険な前例を与えるという懸念もある。北海道は力による現状変更を是とする攻撃に手を染めた米国について「核開発を進める北朝鮮や、台湾への武力行使を否定しない中国に対しても、自らの正当性を主張する格好の口実を与えてしまった」と危ぶみ、京都も「放射能汚染の恐れも顧みない攻撃は、ロシアや北朝鮮の核の脅しに口実を与えかねない」と危機感を示す。
共存共栄へ 行動呼び掛け
米国の振る舞いにより、国際社会の分断や緊張が一層深まることが危惧される。熊本日日は「米国が冷静さを欠いては、国際社会の分断や対立は深まるばかりだ」とし、神戸は「覇権主義こそが今の世界情勢を危機にさらしている元凶だ」と主張。神奈川は「各国が自らの国益を優先するだけでは国際社会は成り立たない。共存共栄のための行動を問い直したい」と呼び掛けた。中日・東京は「カナダでの主要7カ国首脳会議(G7カナナスキスサミット)の共同声明は米国への配慮からイスラエルの自衛権を支持したが、誤りは明白だ」と厳しい目を向け、国際秩序を守る言葉を発するよう求めた。
福島民友は今回の事態が「米国がもはや国際的な秩序を守る側ではなく、他国の主権を踏みにじる側にあることを決定的に示した」と論じ、歴史的な転換であることを指摘する。産経は「中東方面への米軍出動の間隙を突いて、北東アジアで中国が軍事的圧迫を強めてくる事態への警戒も怠れない」と警鐘を鳴らし、米国の軍事行動が他の地域にも波及する安全保障上の緊張に注意を促した。(審査室)