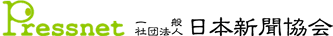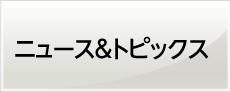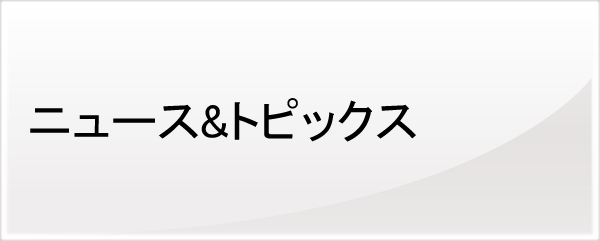- トップページ
- 新聞協会報・紙面モニターから
- 平和の実践 世界に波及を 戦後80年の終戦の日
2025年 9月9日
平和の実践 世界に波及を 戦後80年の終戦の日
次世代への継承課題
戦後80年の節目、「終戦の日」の8月15日付社説では、先の大戦を振り返りつつ、いまの日本政治や世界状況と重ねて日本の果たすべき役割を論じる社が多かった。戦争体験者が減り、記憶を語り継ぐことが難しくなっている中で、「戦後」をこれからもいかに長く続けられるか。ポピュリズム(大衆迎合主義)や排外的なナショナリズムの台頭を危惧する主張も目立った。
「力の支配」 再来を危惧
毎日は、沖縄戦や南京大虐殺の史実に反する発言を政治家が口にし、参院選時には「外国人は優遇されている」「犯罪率が高い」との流言が飛び交ったことを挙げて、「戦争の時代」に時計の針を巻き戻すことがあってはならないと主張。「自国の殻に閉じこもり、他者の窮状を傍観することは許されない。戦後80年の節目に、平和の実践を世界に波及させる行動こそが日本に求められている」と結んだ。
朝日は、大戦の教訓から国際社会は武力の行使を原則禁じ、法によって正義や秩序を保つ「法の支配」を築くと誓ったはずなのに、「力の支配」が再び頭をもたげていると指摘。国際刑事裁判所の所長を日本人が務める背景について、赤根智子所長本人の「日本が戦後一貫して平和主義を貫き、世界で『法の支配』の重要性を発信してきたことが認められた」との言葉も紹介。日本の役割を問うた。
読売は、ロシアによるウクライナ侵略や、イスラエルによるガザ市民の大量殺害に触れて、「日本がそうした現状を傍観し、単に平和の享受者として振る舞い続けることは許されない」と指摘。「秩序の再構築や平和の回復に向け、国際世論を喚起する役割を先頭に立って果たしていくべきだ」と訴えた。
中日・東京は、80年前の終戦時の首相だった鈴木貫太郎の歩みをたどりつつ、いったん始まった戦争を終結させることの難しさを強調した。鈴木が戦後、「戦争放棄」を掲げた憲法9条に敬意を表していたというエピソードも紹介した。
日経は、なぜ先の戦争をしなければならなかったのか、改めて専門家の見解をまじえて紹介。「非合理な判断は司令塔がなく、場の空気に左右される政治体制の影響も大きい。責任の所在が曖昧な集団の判断は、結果責任を問われにくく極端になりがちだ」などと論じた。「自らの歩みを顧み、国際秩序の再構築にどう貢献するかを考えるのも戦後80年の意義」だとした。
国内に残された戦後処理の課題として、空襲で被害を受けた民間人の補償問題を挙げたのは山陽。「被害者の声に真摯に向き合うことは、戦争体験を次の世代へ継承することにもつながる」と訴えた。
茨城は、旧陸海軍施設の保存や若い特攻隊員らの手紙・日記など、「物言わぬ証言者」によって戦争をリアルによみがえらせる試みが県内で広がっていると紹介。「死と隣り合わせの『戦争』が私たちの身近な所でも繰り広げられていたことを地域で語り継いでいきたい」と結んだ。
神戸は、空襲を記録する市民団体が、「活動の担い手を広げないと語り継げない」という問題意識から、戦後生まれや若い世代の参加を促していることを紹介。共同通信の世論調査では、先の戦争を「侵略戦争だった」とした人が42%で10年前から7ポイント減った一方、「自衛の戦争だった」は12%ながら若年層ほど割合が増していることも指摘。「アジア諸国への加害の側面をどう受け止め、伝えていくかも大きな課題だ」と訴えた。
沖タイは「加害者は忘却し、被害者は記憶を継承する。その結果、両者の歴史認識の溝は深まっていく」と指摘。「急速に世界の軍事化が進む今ほど、歴史対話が求められる時はない」と主張した。
「戦争を肌で知る人が減る中、戦争が自らに関係のない『歴史』になり、『日本は悪くなかった』という国民感情が少しずつ目立つようになっているのは確かだろう」と指摘したのは信濃毎日。「『見たいものしか見ない』という楽観主義が、大局的な世界情勢や国力を見誤り、無謀な戦争に突入した大きな要因であることも見過ごしてはならない」と述べた。
報道の役割も論じる
報道のあり方に注文をつけたのは産経。「語り継ぐには相当な努力を要する」としつつ、「改めるべき深刻な問題もある」と指摘。「多くの報道が日本の戦いを侵略と断罪し、異なる見方につながる史実を殆ど伝えてこなかった」「一方的な日本断罪から決別し、先人の歩みをバランスよく知る努力を重ねたい」などと主張した。
戦時報道の反省に立って新聞の役割を論じたのは西日本。1944年に「戦時版」を創刊し、「新聞も兵器である」と、大本営発表そのままに、偽りの戦果を伝え続けたことを振り返り、「改めて過去の事実と責任を受け止め、新聞の役割を心に刻みます」「報国のペンを握った手の感触を忘れず、不戦の未来を描く」と誓った。(審査室)